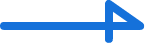酒販免許取得要件に関する情報を掲載しています
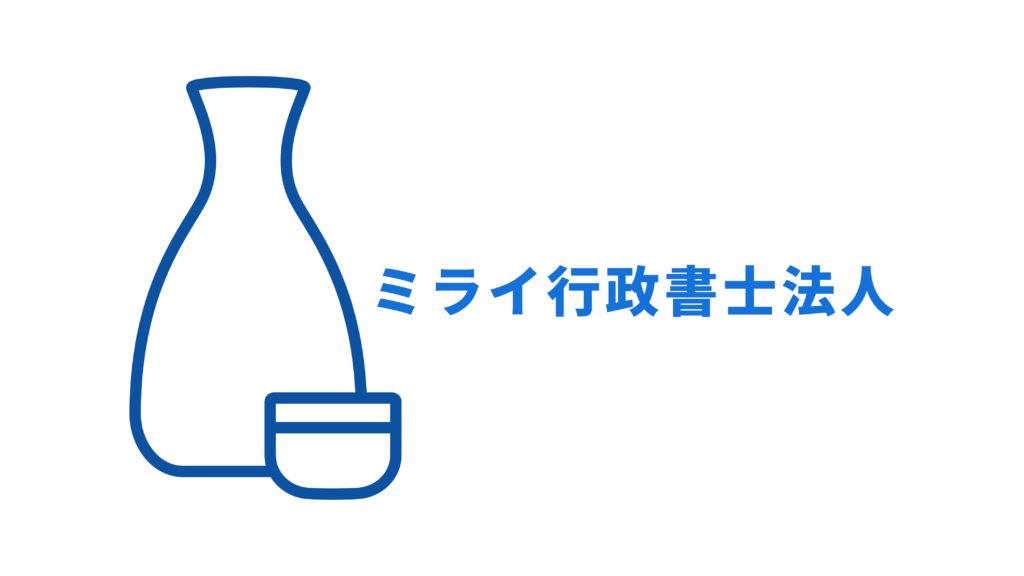
人に対する要件
申請者等に関する人に対する要件は、申請者等(法人については役員、個人については個人事業主)については次のいずれにも該当することが必要です。
・酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと
・酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人の取消原因があった日以前1年以内にその法人の役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること。
・申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
・国税又は地方税に関する法令に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、その刑の執行を終わり若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
・20歳未満の者の飲酒禁止に関する法、風俗営業法(未成年者に対する酒類の提供に関する部分のみ)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、暴行、脅迫等)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり若しくは執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
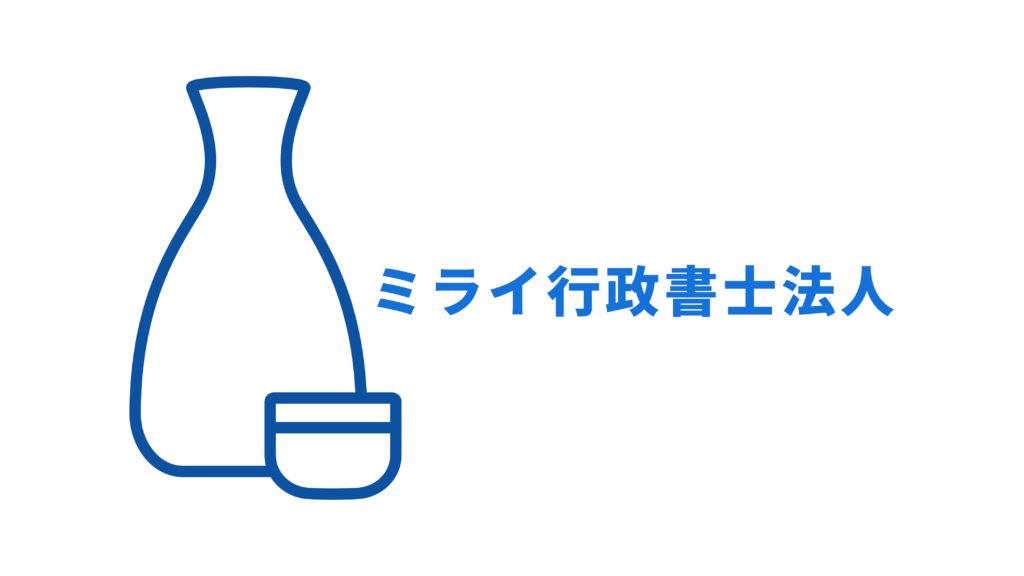
一般酒類小売業免許について
解釈通達による一般酒類小売業免許の取扱い
経歴及び経営能力等
申請者等(申請者等が法人の場合はその役員)及び申請等販売場の支配人がおおむね次に掲げる経歴を有する者であって、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合は原則としてこの定めを満たすものとして取り扱われます。
・酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間が引き続き3年以上である者
・調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者
・酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者
・酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者
※なお、これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、
1.酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験
2.税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等
酒類の小売業を経営するのに十分な知識及び能力が備わっているかどうか実質的に審査されます。
(この場合は、それぞれの事例ごとに税務署の個別判断となります。)
※販売経験3年以上という要件は例示規定であり、それらの要件を要求されない地域もありますし、要求される地域もあります。詳しくはお問い合わせください。
※今では酒類販売管理研修の受講をしていれば経験は必要ありません。
販売能力及び所要資金等
申請者等は、申請等販売場において酒類を継続的に販売するための所要資金を賄うに足りる所有資金等並びに必要な販売施設及び設備を有している者又は所有資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められる者であること。
※資金は2ヶ月分の酒類仕入資金があるかどうかになります。
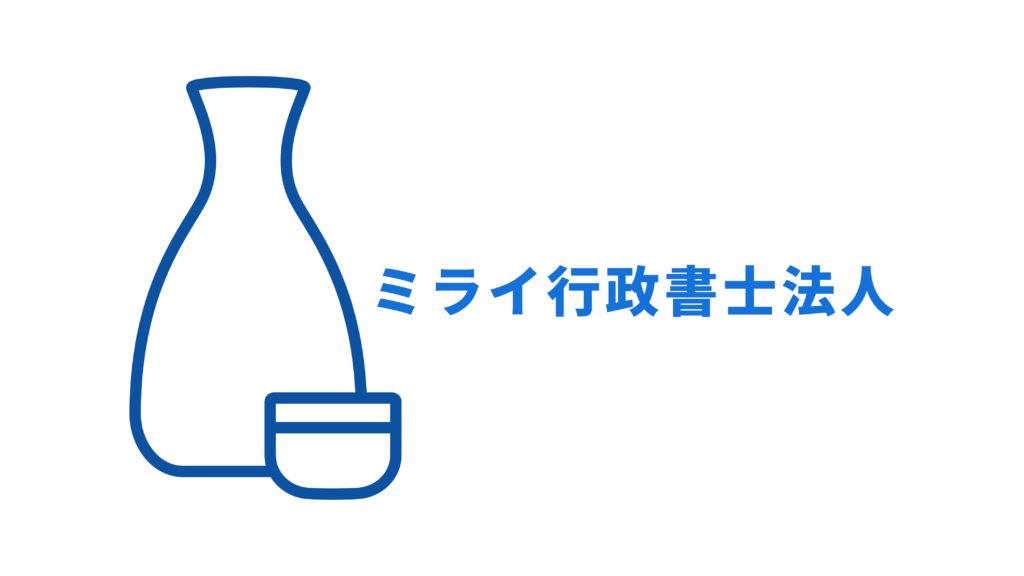
通信販売酒類小売業免許について
解釈通達による通信販売酒類小売業免許の取扱い
経歴及び経営能力等
申請者等(申請者等が法人の場合はその役員)及び申請等販売場の支配人が、経験その他から判断し、適正に酒類の通信販売を行うための十分な知識、経営能力及び販売能力を有すると認められる者は原則としてこの定めを満たすものとして取り扱われます。
・申請書類に添付するホームページのサンプル画面によって判断されます。通信販売の経験もプラスの要因にはなりますが現在は酒類販売管理研修の受講とサンプル画面の記載方法で適正に酒類の通信販売を行うための十分な知識、経営能力及び販売能力を満たします。
※なお、これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、
1.酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験
2.税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等
酒類の通信販売小売業を経営するのに十分な知識及び能力が備わっているかどうか実質的に審査されます。
(この場合は、それぞれの事例ごとに税務署の個別判断となります。)
※通信販売経験という要件は現在、要求されない地域がほとんどです。詳しくはお問い合わせください。
※現在は酒類販売管理研修を受講すれば上記経験は必要ありません。
販売能力及び所要資金等
申請者等は、酒類の通信販売を行うための所要資金等を有し、販売方法が特定商取引に関する法律の消費者保護関係規定に準拠し、「20歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」を満たし、又はこの定めを満たすことが確実であると見込まれるもの。
申請者等は、酒類の購入申込者が20歳未満の者でないことを確認できる手段を講ずるものと認められること。
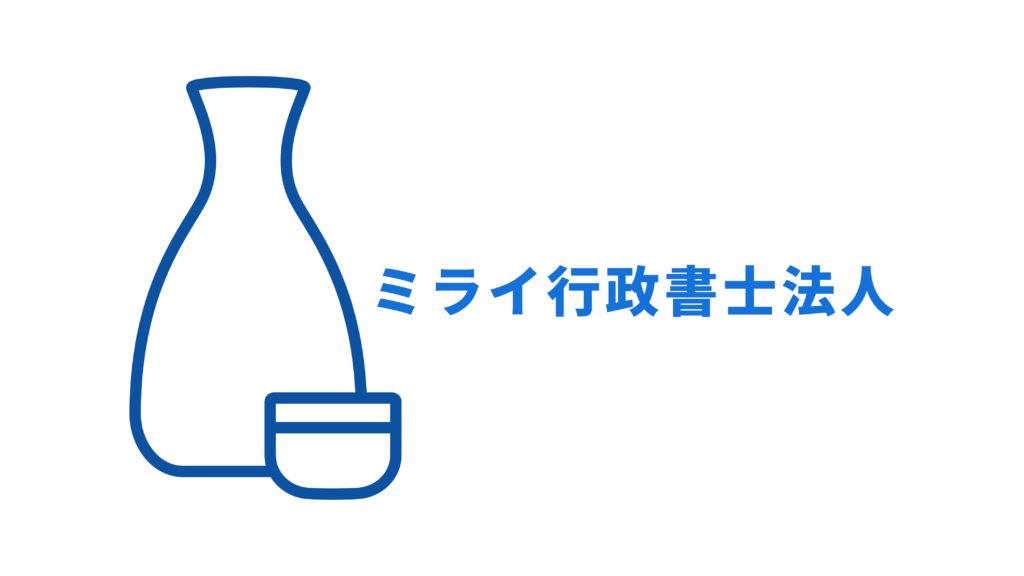
洋酒、店頭販売酒類、自己商標卸売業免許とその取得について
解釈通達による洋酒卸売業免許、店頭販売酒類卸売業免許、協同組合員間酒類卸売業免許及び自己商標卸売業免許の取扱い
経歴及び経営能力等
申請者等は、経験その他から判断し、適正に酒類の卸売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が役員で組織する法人の場合は、原則としてこの定めを満たすものとして取り扱われます。
酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の卸売業を経営するのに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められること。
・酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間が引き続き3年以上である者
・調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者
・これらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者
・酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者
・酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者
※なお、酒類の製造業や販売業に直接従事した経験や調味食品等の販売業経営経験がない場合でも、その他の業種での経営経験と役員の酒類販売管理研修受講などから、
① 酒類の特性に応じた商品管理上の知識と経験
② 酒税法上の記帳義務など酒類販売業者としての義務を適正に行うことができる知識と能力等
①と②から酒類の卸売業免許を経営するのに十分な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に判断されます。
※販売経験3年以上という要件は例示規定であり、その要件を要求されない地域もありますし、要求される地域もあります。詳しくはお問い合わせください。
※上記の経験がなくても免許交付となったケースを東京、千葉、神奈川や大阪、滋賀、兵庫、福岡など全国で数多く手掛けております。一度お問い合わせください。
所要資金等
申請者等は、月平均販売見込数量、月平均在庫数量、平均在庫日数、平均売上及び設備等を勘案して酒類卸売業を経営するに十分と認められる所要資金等を有している者であること。
2ヶ月分の酒類仕入資金があるかどうかになります。
設備
申請者等は、販売見込数量から勘案して適当と認められる店舗、倉庫、器具及び運搬車等の販売施設及び設備を有し又は有することが確実と認められる者であること。
洋酒卸売業免許について
洋酒卸売業免許とは、酒類のうち果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、雑酒、粉末酒の卸売ができるようになる免許です。ただ雑酒と粉末酒については、現在あまり流通していないので不要かと思いますが、リサイクルショップなどではかなり昔の紹興酒などは裏ラベルに雑酒と記載があるものもありますから、条件に入れておくと良いでしょう。
洋酒卸売業免許を取得すると、酒類製造業者や酒類卸売業者(リサイクルショップなどでは同業者)から仕入をすることができ、酒類卸売業者や酒類小売業者(リサイクルショップなどでは同業者やFC本部)に販売をすることができる免許です。
店頭販売酒類卸売業免許について
店頭販売酒類卸売業免許とは、すべての酒類を自社の会員に対して、店頭で卸売することができます。毎年抽選の全酒類卸売業免許の取得と比べると簡単に取得でき、さらにすべての酒類を酒類卸売業者や酒類小売業者(リサイクルショップなどでは同業者)に販売することができます。
洋酒卸売業免許では販売することができない日本酒や焼酎、ビール、みりんも卸売することができます。
自己商標酒類卸売業免許について
自己商標酒類卸売業免許とは、自社で開発した商標又は銘柄についてのみ卸売することができる免許です。OEMで製造された酒類などを卸売する場合で日本酒や焼酎、ビール、みりんの場合はこの免許が良いでしょう。
日本酒や焼酎、ビール、みりんを卸売する場合は、全酒類卸売業免許を取得しないと卸売が難しいので、自己商標酒類卸売業免許が良いです。
果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュールに自己の商標又は銘柄をつけて卸売する場合は、洋酒卸売業免許の取得の方が販売できる範囲も広いのでそちらの取得をおすすめいたします。
この自らが開発した商標又は銘柄というのは、自らが取得している商標でないと取得できないというわけではありません。よく勘違いされている方は多いのですが、商標登録していないといけないとか自社で商標を取得していないと取得できないなどよく聞きますが、商標の登録はあくまで商標保護のためです。
「自らが開発した商標又は銘柄」の酒類なので、自ら開発した商標や自ら開発した銘柄であればよいです。
商標登録証を提出するのは自ら開発した商標だということを証明しているだけに過ぎません。
自ら開発した商標であることや自ら開発した銘柄であることが書類で証明できれば、この自己商標酒類卸売業免許を取得できます。
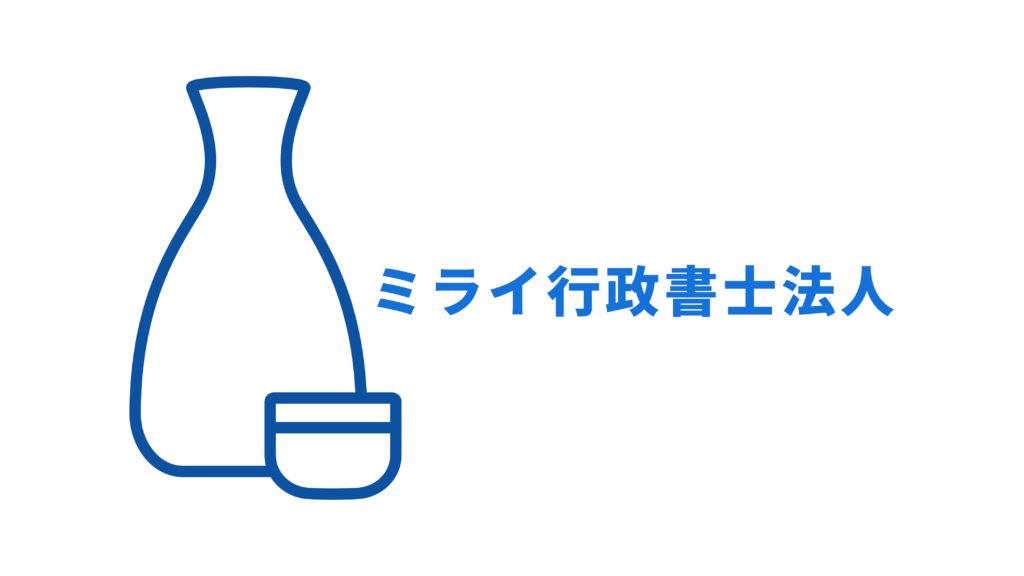
輸出入酒類卸売業免許とその取得方法について
輸出入酒類卸売業免許について
お酒の輸出や輸入をしようとする場合、輸出酒類卸売業免許または輸入酒類卸売業免許が必要になります。
現在の財務状況については、他の免許と同じ条件ですが、経験条件が緩く、輸出または輸入をすることが確実であると認められるなら免許交付となる点で他の酒販免許よりも比較的とりやすい免許だと言えるでしょう。
具体的には輸出先、仕入先の契約書等、輸入先、販売先の契約書等の提出が求められますので、免許申請の際にはある程度具体的に輸出や輸入をすることが確定している必要があります。
また、これらの免許交付は申請後2ヶ月以内となりますので、輸出、輸入を検討された際には専門家に相談することをお勧めします。
解釈通達による輸出入酒類卸売業免許の取扱い
経歴及び経営能力等
申請者等が、外国人である場合は外国人登録法に規定する外国人登録証明書を有している、また、外国法人である場合は日本において支店登記が完了していることが必要です。
販売能力及び所要資金等
・一定の店舗(事務所)を有していること。
輸出酒類卸売業免許については、次のいずれにもあてはまること。
・契約等により酒類を輸出することが確実と認められる。
・輸出酒類卸売業を経営するに十分と認められる所要資金等を有している。
輸入酒類卸売業免許については、次にあてはまること。
・契約等により酒類を輸入することが確実と認められる。
・輸入酒類卸売業を経営するに十分と認められる所要資金等を有している。
(注)輸出又は輸入が1回限り等取引回数が限定されている場合であっても、それをもって輸出入酒類卸売業免許の拒否の理由とはされません。
(注)輸出又は輸入の契約内容が確定するまでには至っていない場合であっても、輸出又は輸入が行われることが確実であると認められるときは、輸出入酒類卸売業免許を付与等されることがあります。
契約等により酒類を輸出、輸入することが確実と認められる場合とは
実際に免許もないのに確実と認められるような契約なんてできない!と思われるかもしれません。
この契約等により酒類を輸出、輸入することが確実と認められる場合というのは、必ずしも契約書を交わすというような大それたものでなくてはならないわけではありません。
輸出、輸入が確実であるということは、ある程度仕入先や輸出先、輸入先が確定しているということを証明すれば良いということになります。
これから輸出や輸入をはじめようとする方で、仕入先や輸出先、輸入先がまったく決まっていないなんてことはありませんよね。この条件を満たすためには、仮でもよいので契約を締結するか、取引の承諾をもらうかをすればよいです。
その書式も難しく考えず、
『当社が製造する酒類を〇〇へ販売することを承諾する。ただし、〇〇が輸出(輸入)酒類卸売業免許を取得できない場合は、本承諾は効力を有しない。』
『〇〇が販売する酒類を、取引することを承諾する。ただし、〇〇が輸出(輸入)酒類卸売業免許を取得できない場合は、本承諾は効力を有しない。』などというような内容で大丈夫です。
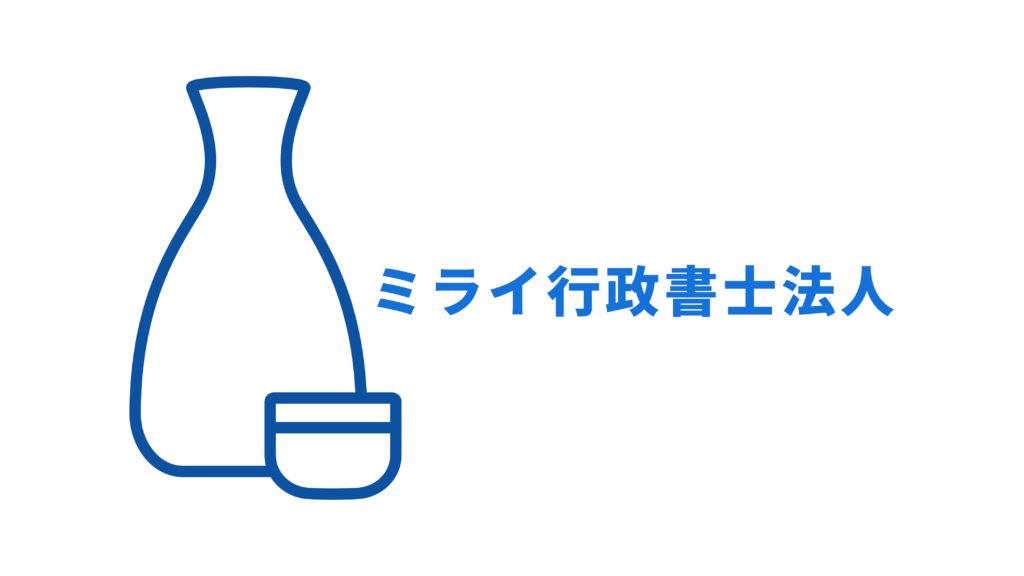
免許取得場所の条件
免許取得場所の条件
免許は販売場ごとに取得する必要があります。
酒税法10条9号には場所的要件として以下のように定められています。
正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしないこと
具体的には、
・製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場または料理店等と同一の場所でないこと。
(注)申請製造場が酒場、料理店等と接近した場所である場合、必ず図面上で明確に区分させる。この場合、検査取締役上特に必要があると認められるときには、製造場と酒場、料理店等とを壁、扉等で区分する。
・申請販売場における営業が、販売場の区画割り、酒販専属の販売者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること。
(注)たとえば、狭い店舗内の一部を賃借して陳列棚を販売場とする場合などは、明確に区分されているとは認められない。また他の業者と同一のレジスターにより代金決済をする場合も認められない。
酒類の移動販売の取扱い
一定の販売場を設けず、自己の住所等を根拠として酒類を携行し、または運搬車、舟等に掲載して随時随所において注文を受け、酒類を引き渡し、または酒類の販売代金を受領する等の方法により酒類の小売を行う移動販売については、当分の間付与されません。
自動販売機による酒類小売業免許の取扱い
自動販売機のみによって酒類を小売しようとする場合は、未成年者飲酒防止及び交通事故防止の観点から、原則として酒類小売業免許は付与されない。
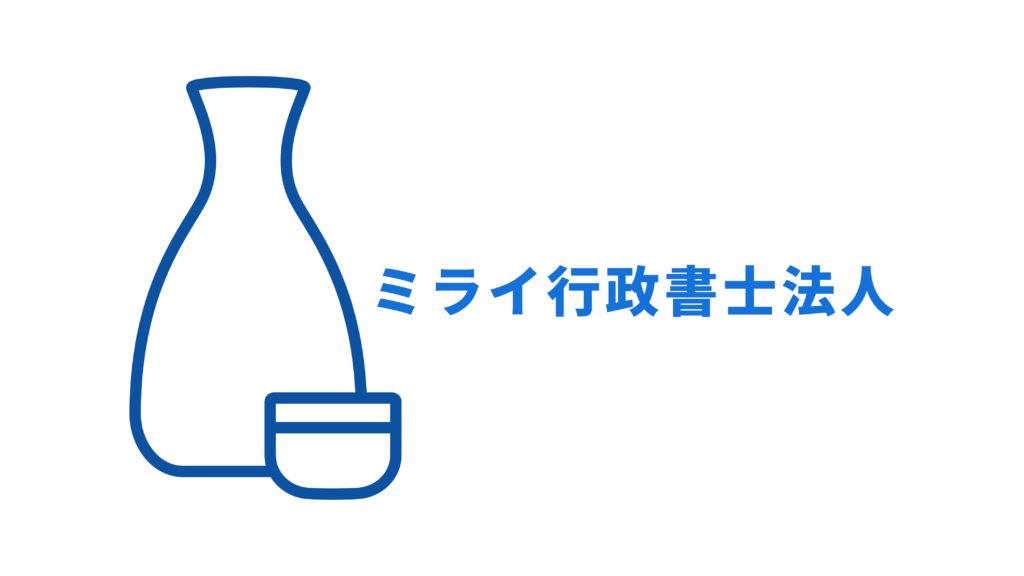
経営状態に関する条件
酒税法10条10号では、以下のように定められています。
1.免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合
2.その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと
「経営の基礎が薄弱でないこと」とは、具体的には、次のことをいいます。
申請者等が次のに掲げる場合に該当しないかどうか
(注) 申請者等とは、申請者が法人のときは代表者又は主たる出資者をいいます。
・現に国税若しくは地方税を滞納している場合
・申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
・最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
・最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
(注) 「資本等の額」=資本金+資本剰余金+利益剰余金-繰越利益剰余金
・酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
・販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却若しくは移転を命じられている場合
・申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合
さらに申請者が、次の要件を満たしているかどうかでも判断します。
・申請者は、経験その他から判断し、適正に酒類の販売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること。
(注) 申請者(申請者が法人の場合はその役員)及び申請販売場の支配人が次に掲げる経歴を有する者で、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を 経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合は、原則として、この要件を満たすものとして取り扱うこととしています。
1.免許を受けようとする酒類の製造業の業務経験3年以上
2.免許を受けようとする酒類販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)業務経験3年以上
3.調味食品等の販売業の業務経営経験3年以上
4.酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者
5.酒類の製造業経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者
6.酒類の販売業経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情 に十分精通していると認められる者
・申請者は、酒類を継続的に販売するために必要な資金、施設及び設備を有していること又は必要な資金を有し、申請がなされた免許年度の終了日までに施設及び設備を有することが確実と認められること。
※これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、
1.酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験
2.税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等
酒類の販売業を経営するのに十分な知識及び能力が備わっているかどうか実質的に審査されます。
(この場合は、それぞれの事例ごとに税務署の個別判断となります。)
※販売経験3年以上という要件は現在、要求されない地域もありますし、要求される地域もあります。詳しくはお問い合わせください。
※ 酒類販売の継続性及び「20歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」その他の法令遵守の可能性について、事業もくろみ書や申請者からの聴取等により確認されます。
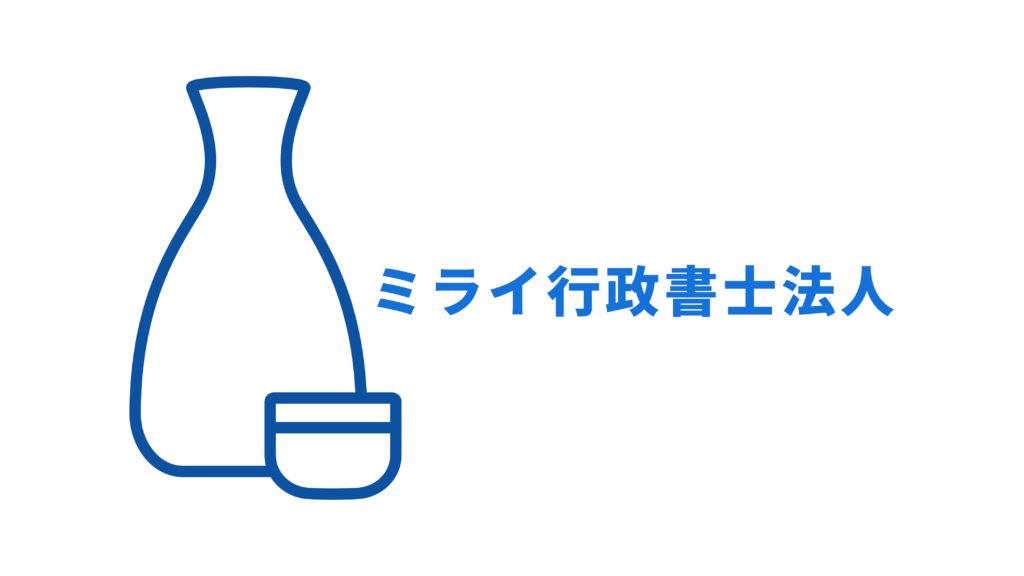
需給調整要件
一般酒類小売業免許の需給調整要件
次のいずれかに該当する者には、当分の間、一般酒類小売業免許が付与されない。
・設立の主旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体。
ただし、その法人又は団体の申請等販売場の所在地の周辺地域内に居住している住民の大半が、これらの法人又は団体の構成員となっている場合で、その近辺に一般酒類小売販売場がなく、消費者の酒類の購入に不便であり酒類の需給状況からみてもこれらの者に免許を付与等する必要があり、かつ、これらの者が酒類小売業を営んでも、適正な酒類の取引を損なうおそれがないと認められるときはこの限りではない。
・酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者(接客業者の組合等を含む。)。ただし、国税局長において免許を付与等することについて支障がないと認めた場合を除く。
通信販売酒類小売業免許の需給調整要件
・通信販売酒類小売業免許は、販売しようとする酒類の範囲が、カタログ等の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である製造者が製造、販売する酒類又は輸入酒類である場合には免許が付与される。
(注)「カタログ等」とは、いわゆるカタログのほか、チラシ等若しくは雑誌新聞又はインターネットによる広告等をいう。
(注)前会計年度における課税移出実績がない場合は、カタログ等の発行日の属する会計年度における製造者の製造見込数量により判断される。
(注)通信販売により販売できる酒類かどうかについては、通信販売を予定している製造者の発行する証明書(通信販売の対象となる酒類であることの証明書をいう。)を申請書等に添付が必要となります。
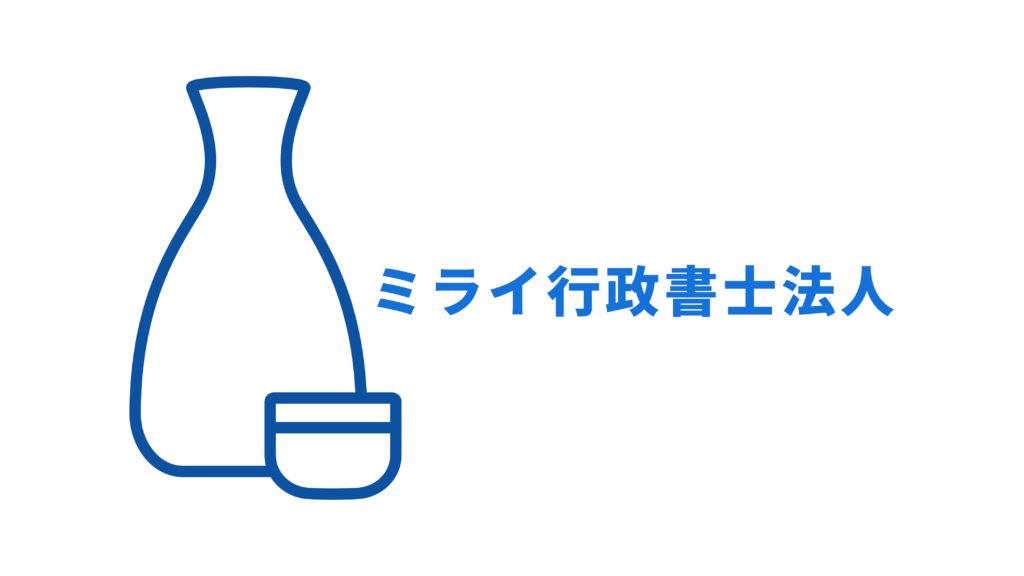
薬用酒の販売業免許
1.薬用酒のみの酒類販売業をしようとする場合は、次のいずれかに該当する薬用酒の販売場を除き、酒類販売業免許を受ける必要はないものとして取り扱う。
薬用酒製造者の販売場
薬用酒輸入販売業者の販売場
薬用酒製造者から直接薬用酒を仕入れ、これを他の薬用酒販売業者に販売する酒類卸売業者の販売場
(支店、出張所等のうち、薬用酒製造者との直接取引は行わず、酒類販売業免許を受けている自己の他の販売場を通じて薬用酒を仕入れる販売場を除く。)
2.薬用酒の卸売業に対する免許
薬事法の規定により都道府県知事から医薬品の販売業の許可を受けている者から、その許可を受けてい る店舗と同一場所において薬用酒を卸売するため酒類卸売業免許の申請がある場合は、年平均販売見込数量の定めに かかわらず免許の可否を判定し、支障がないと認められるときは、免許を付与しても差し支えないとされています。
※その他薬用酒についての特例
薬用酒のみの販売業は全酒類卸売業免許取得と酒類販売媒介業免許取得についての経歴および経営能力等を判断するための経験経験(10年)には含まれません。
薬用酒のみの販売業は一般酒類小売業免許取得についての経歴および経営能力等を判断するための経験経験(3年)には含まれません。
薬用酒のみの販売場には、酒類販売管理者を選任する必要ありません。
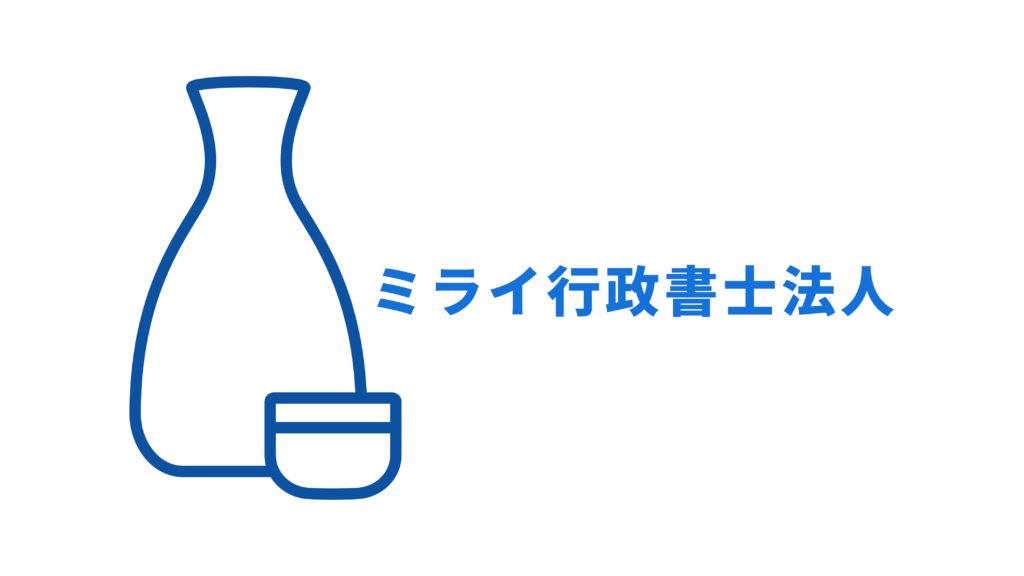
酒類販売代理業免許
酒類販売代理業
酒類販売代理業とは、製造者又は酒類販売業者の酒類の販売に関する取引を継続的に代理する者であって、営利を目的とするかどうかは問わないもの。
代理業者と使用人の区別
代理業者と使用人の区別は、営業所の所有関係、営業費の分担関係及びその者が受ける報酬が手数料であるか定額報酬であるか等の事実関係を総合して判定されます。
酒類販売代理業の取扱い
酒類販売代理業免許の取扱い
・申請者が代理を行う酒類販売業者の酒類販売業免許に係る酒類販売業務以外の業務についての代理業は行わない旨の誓約がある場合は、代理を行う酒類販売業者の酒類販売業免許の区分に従い、免許の可否が決定されます。
・代理を行う酒類販売業務について誓約がない場合は、酒類販売業免許のすべての取扱いに従い、免許の可否が決定されます。
・上記いずれにもかかわらず申請者が輸出先又は輸入先の代理店として酒類販売の代理業を営む場合であって、かつ、輸出入酒類卸売業免許を付与できる者であるときは、酒類販売代理業免許を付与されます。
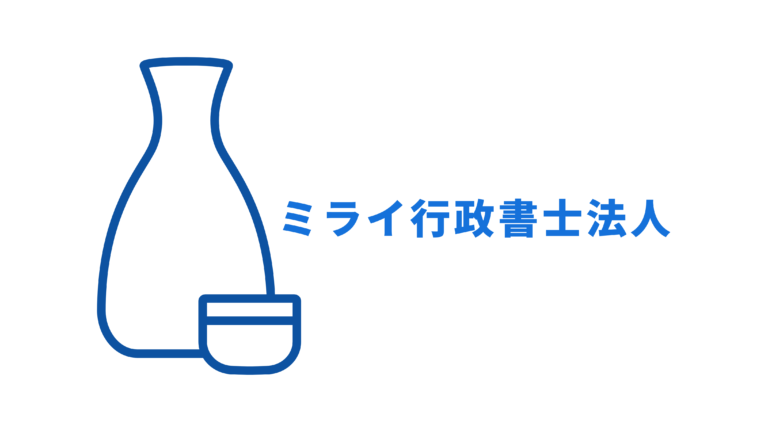
酒類販売媒介業免許とその取得について
酒類販売媒介業
酒類販売媒介業とは、他人間の酒類の売買取引を継続的に媒介(取引の相手方の紹介、意思の伝達又は取引内容の折衝等その取引成立のためにする補助行為をいう。)することであって、営利を目的とするかは問わない。
例えば、コールセンターで受注を委託される場合には酒類媒介業免許が必要です。その他お酒の競り売り(オークション)なども酒類媒介業免許が必要となります。
酒類販売媒介業については、税務署審査に4ヶ月ほどかかり、登録免許税が9万円かかります。
酒類販売媒介業の免許取得条件
共通する条件はこちら
場所的な条件はこちら
破産者で復権を得ていないものでないこと
地方税及び国税を滞納していないこと
過去1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと
直近の決算書に基づく貸借対照表の繰越欠損が資本等の額(資本金+資本準備金+利益準備金)を上回っていないこと
直近3期分の決算書のすべて、資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていないこと
酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受けたが、履行していること又は告発されていないこと
販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却若しくは移転を命じられていないこと
申請酒類販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかでないこと
媒介業を営むに足る事務所及び電話その他の設備を有し、又は有することが確実と認められること
必要とされる経験
免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に従業員として直接従事した期間が引き続き10年(これらの事業の経営者として直接業務に従事した者にあっては5年)以上である者
過去において酒類販売媒介業免許を取得し、相当期間経営したことがある者
酒類の副産物、原料、醸造機械等の販売業の業務に、従業員として直接従事した期間が引き続き10年以上である者
酒類の製造技術の指導等の経験を5年以上有している者
※上記の経験5年以上や10年以上という要件は例示規程であり、その要件を要求されない地域もありますし、要求される地域もあります。詳しくはお問い合わせください。5年や10年の経験がなくても免許交付された実績があります。
必要とされる販売能力
申請者の年平均の取扱見込数量は100キロリットル以上であることが確実であり、継続して媒介業を行う見込みがある。
※この年間取扱見込数量がなくても、他商品で媒介業の実績、継続して媒介業を行うとわかるような資料があれば100キロリットルの見込みは不要です。
事務所、電話、FAX、パソコン等の設備があること。
酒類販売媒介業免許の取扱い
・酒類販売媒介業免許は、その媒介のための事務所の所在する場所ごとに免許を必要とします。
(注)酒類販売媒介業免許を受けた場所には、酒類の媒介業者の事務所である旨を表示させなければならない。
この免許は、お酒の販売でコールセンターのような業務を行う場合やオークション(いわゆる競り売り)を行う場合に必要となってくる免許になります。実際に酒類販売媒介業を行う場合、媒介をする業者の酒類販売業免許の通知書を確認するなど免許があることやそのお酒を販売することができるのか十分に確認することができるスキームが求められます。
申請後の審査では、国税庁も審査を行うため、通常の酒類販売業免許申請よりも細かい書類が必要となる場合もあります。当事務所ではこの酒類販売媒介業免許についても全国で実績多数ありますので、安心してご相談ください。
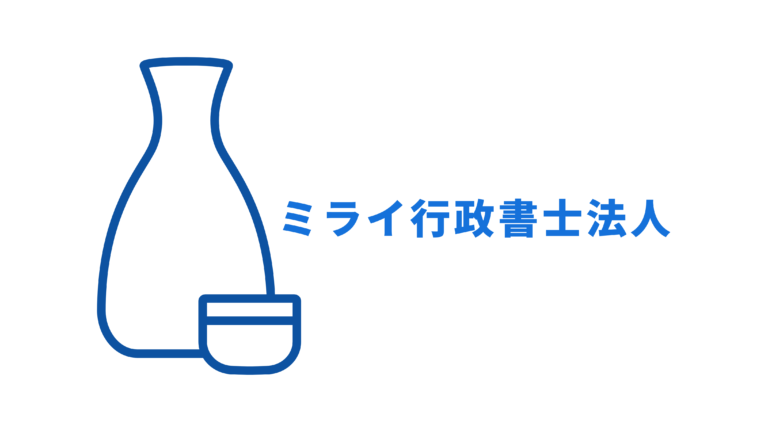
期限付酒類販売業免許
期限付酒類小売業免許申請について
期限付酒類小売業免許は、申請者が酒類製造者または酒類販売業者であり、地域の特産物や新製品、贈答品などの即売会場や酒類製造者の自製酒、酒類販売業者が輸入した酒類、自己商標酒類などの販売を行う即売会場、競技場、遊園地、キャンプ場、海水浴場等臨時に人の集まる場所や工事現場、遊覧船内などで臨時に販売場を設けて酒類の小売を行うこと際に必要な免許になります。
①この期限付酒類小売の免許申請の目的が、特売や在庫処分でないこと。
②契約等により、販売場の設置場所が特定されていること。
③開催期間、開催日が予め定められていること。
④酒類製造者の自製酒、酒類販売業者が輸入した酒類、自己商標酒類などの販売を行う場合、1回の開催期間が概ね2週間以内で、同じ場所で開催することが年6回以内であること。
申請は、臨時の販売場を開設する2週間前までに行います。
なお、期限付きであっても免許の期限延長をすることもできる場合があります。
届出による期限付酒類小売業免許について
酒類製造者または酒類販売業者が臨時で販売場を設け酒類の小売を行う場合で、次のすべてに該当し、臨時に販売場を開設する10日前までに、届出を行います。
これは同じ申請者で同じ場所での届出は、入場料を取るような場合でない限り、月1回に限ります。
①あらかじめ定められている開催期間が7日以内で客観的に明瞭である
②催物の主目的が酒類の小売ではない
③酒類の小売目的が特売や在庫処分ではない
④契約等により、臨時販売場の設置場所が特定されている
⑤販売する酒類の範囲は、現在受けている免許の条件と同一である
⑥酒類の配達をしないこと
期限付酒類卸売業免許
期限付酒類卸売業免許は、製造者または酒類販売業者(酒類を卸売することができる販売場を有する者に限る。)について,次のいずれの要件も満たした場合に、適切に期限並びに販売する酒類の範囲及びその販売方法について条件を付され、期限付酒類卸売業免許を付与される。
①新製品の広告宣伝のために臨時に展示等即売会場を設けて酒類の卸売を行おうとする
②1階の展示等即売会の開催期間が5日以内であり、かつ、新製品の販売後おおむね1ヶ月までの間に開催する
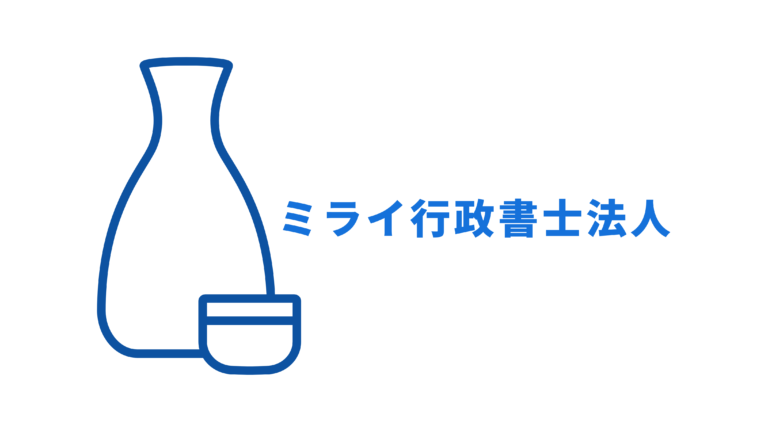
輸出用清酒製造免許とその取得方法
「日本酒」の輸出拡大に向け、令和3年4月から新たに創設された酒類製造免許になります。
今までの製造免許のように清酒最低数量基準60klが適用されないため、少量の製造からでもこの製造免許の取得が可能となります。
ただし、米及び米こうじに国産米を用いて製造しなくてはなりません。
この免許の創設により、高付加価値をつけた日本酒の少量製造も可能となり、日本酒のブランド化、ブランド価値の確保・向上を図ることとされています。
輸出用清酒製造免許を取得して、製造した清酒(日本酒)は原則輸出用であり国内販売はできません。次の場合で輸出するために必要な行為として無償で提供する場合に限り、国内への課税移出(酒税は課税されます。)が可能です。
・国内で開催される輸出のための商談会等に使用する場合、
・商社等の輸出業者へサンプルとして提供する場合、
・国税局が実施する品質審査等に提出する場合など
輸出用清酒の未納税移出(酒税の免税)について
輸出用清酒製造場から輸出のために出荷するため、
・輸出業者の輸出酒類蔵置場へ出荷する場合
・輸出するまでの間、自己の他の酒類の製造場又は蔵置場へ出荷する場合
・容器詰めのため、他の酒類製造者の製造場又は蔵置場へ出荷する場合
・容器詰めのため、他の酒類製造者の製造場又は蔵置場へ出荷され、その清酒を自己の酒類製造場又は蔵置場へ出荷する場合
・輸出用清酒の原料として使用する酒類(清酒を除く)を出荷する場合
酒税法上の清酒とは
・米、米こうじ及び水を原料として発酵させて、こしたもの
・米、米こうじ、水及び清酒かすその他政令で定める物品を原料として発酵させて、こしたもの(その原料のうち、政令で定める物品の重量が米、米こうじの重量の50%を超えないものに限る。)
・清酒に清酒かすを加えて、こしたもの
清酒の原料となる糖類には「ぶどう糖以外の糖類ででん粉質物を分解したもの」とあり、これは水あめの他、米を原料として加水分解して精製した糖類のことです。
輸出用清酒製造免許の人的要件
1.申請者が酒類等の製造免許若しくは酒類販売業免許又はアルコール事業法の許可取消処分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年経過していること
2.申請者が酒類の製造免許または酒類の販売業免許、アルコール事業法の許可の取り消し処分を受けたことがある法人の役員で、取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
3.申請者が申請前2年以内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
4.申請者が国税又は地方税に関する法令に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、罰金の執行を終わり又は通告の履行をした日から3年を経過していること
5.申請者が、法令に違反し、罰金刑、禁錮以上の刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
場所的要件
輸出用清酒製造免許の製造場が酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと
経営基礎要件
酒税法10条10号では、以下のように定められています。
1.免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合
2.その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと
「経営の基礎が薄弱でないこと」とは、具体的には、次のことをいいます。
申請者等が次のに掲げる場合に該当しないかどうか
(注) 申請者等とは、申請者が法人のときは代表者又は主たる出資者をいいます。
・現に国税若しくは地方税を滞納している場合
・申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
・最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
・最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
(注) 「資本等の額」=資本金+資本剰余金+利益剰余金-繰越利益剰余金
・酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
・製造場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却若しくは移転を命じられている場合
・清酒の製造免許を付与された場合において、当該製造者が今後1年間に納付すべき酒税額の平均3ヶ月分又は製造免許申請書に記載している清酒の製造予定数量に対する酒税相当額の4ヶ月分のうち、いずれか多い方の金額以上の担保を提供する能力がないと認められる場合
・申請者、その役員が事業経歴その他から判断し、適正に清酒を製造するのに十分な知識及び能力を有すると認められる者
・申請者が、清酒を適切に製造するために必要な所要資金等並びに製造又は貯蔵等に必要な設備及び人員を有する者であって、清酒の製造に関して安定的な経営が行われると認められる場合であること(通帳のコピーなど資金を証明する書類が必要)
・清酒の製造に必要な原料の入手が確実と認められること
(仕入先との取引承諾書などで証明します。)
・申請者(従業員を含む)がこれまで食品等を輸出した経験があること
(履歴書記載の職務経歴などで判断されます。)
・申請者が海外における取引先等の輸出先を確保していること
(輸出先との取引承諾書などで証明します。)
製造技術・設備要件
1.技術的要件
申請者は、醸造・衛生面等の知識があり、かつ保健衛生上問題のない一定水準の品質の酒類を継続的に供給することができ、不測の事態が生じた場合に対応できる能力を有すること
※製造計画や製造工程、製造技術者の経歴、人員、品質設計、品質管理、研修の体制等から総合的に判断されます。必要な技術的能力をもっている方を雇用することで技術的能力は満たします。
2.設備要件
酒類の製造又は貯蔵等に必要な機械、器具、容器等(精米機やしぼり機、瓶詰機、麹室など)が十分備わっていることと、製造場が工場立地法、下水道法、水質汚濁防止法、食品衛生法等製造場の設備に関する法令等に抵触していないこと
他の法令で許可等が必要な場合もあります。
当事務所では全くの未経験の方の酒類製造のご支援等も行っております。酒類の製造業をご検討の方は、ぜひ一度ご相談ください。
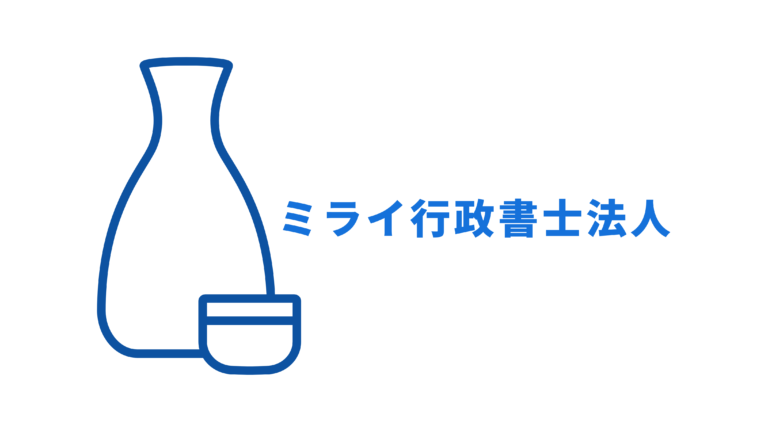
酒類製造業免許の取得方法
酒類製造の最低製造見込数量
酒類の製造免許は、ひとつの製造場で1年間に製造しようとする酒類の見込数量が、酒類の品目ごとに定められています。これは申請時点で製造数量を生産することができる設備が必要となるということです。
1.清酒 60kl
2.合成清酒 60kl
3.連続式蒸留焼酎 60kl
4.単式蒸留焼酎 10kl
5.みりん 10kl
6.ビール 10kl
7.果実酒 6kl
8.甘味果実酒 6kl
9.ウイスキー 6kl
10.ブランデー 6kl
11.原料用アルコール 6kl
12.発泡酒 6kl
13.その他の醸造酒 6kl
14.スピリッツ 6kl
15.リキュール 6kl
ただし、複数の酒類、例えば、ウイスキーとリキュールをひとつの製造場で製造しようとする場合には、その製造見込数量合計が12kl必要ではなく、ひとつの製造場で6klの製造見込数量があれば、満たすことになります。
上記の製造見込数量の多い方を優先しますので、清酒とリキュールを製造しようとする場合には年間製造見込数量60klを満たさなければなりません。
構造特区等の場合には上記製造見込み数量がないこともあります。
酒類製造免許の人的要件
申請者が酒類等の製造免許若しくは酒類販売業免許又はアルコール事業法の許可取消処分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年経過していること
申請者が酒類の製造免許または酒類の販売業免許、アルコール事業法の許可の取り消し処分を受けたことがある法人の役員で、取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
申請者が申請前2年以内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
申請者が国税又は地方税に関する法令に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、罰金の執行を終わり又は通告の履行をした日から3年を経過していること
申請者が、法令に違反し、罰金刑、禁錮以上の刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
場所的要件
酒類製造免許の製造場が酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと
これらと同じ場所の場合には明確に区分けを行い、事業としてもそれぞれ独立させる必要があります。
経営基礎要件
酒税法10条10号では、以下のように定められています。
1.免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合
2.その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと
「経営の基礎が薄弱でないこと」とは、具体的には、次のことをいいます。
申請者等が次のに掲げる場合に該当しないかどうか
(注) 申請者等とは、申請者が法人のときは代表者又は主たる出資者をいいます。
・現に国税若しくは地方税を滞納している場合
・申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
・最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
・最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
(注) 「資本等の額」=資本金+資本剰余金+利益剰余金-繰越利益剰余金
・酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
・製造場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却若しくは移転を命じられている場合
・酒類の製造免許を付与された場合において、当該製造者が今後1年間に納付すべき酒税額の平均3ヶ月分又は製造免許申請書に記載している酒類の製造予定数量に対する酒税相当額の4ヶ月分のうち、いずれか多い方の金額以上の担保を提供する能力がないと認められる場合
・申請者、その役員が事業経歴その他から判断し、適正に酒類を製造するのに十分な知識及び能力を有すると認められる者
・申請者が、酒類を適切に製造するために必要な所要資金等並びに製造又は貯蔵等に必要な設備及び人員を有する者であって、酒類の製造に関して安定的な経営が行われると認められる場合であること(通帳のコピーなど資金を証明する書類が必要)
・酒類の製造に必要な原料の入手が確実と認められること
(仕入先との取引承諾書などで証明します。)
・申請者(従業員を含む)がこれまで醸造等食品や酒類の製造業に従事した経験があること
(履歴書記載の職務経歴などで判断されます。)
・申請者が製造した酒類の販売をする取引先等を確保していること
(販売先との取引承諾書などで証明します。)
製造技術・設備要件
技術的要件
申請者は、醸造・衛生面等の知識があり、かつ保健衛生上問題のない一定水準の品質の酒類を継続的に供給することができ、不測の事態が生じた場合に対応できる能力を有すること※製造計画や製造工程、製造技術者の経歴、人員、品質設計、品質管理、研修の体制等から総合的に判断されます。必要な技術的能力をもっている方を雇用することで技術的能力は満たします。
設備要件
酒類の製造又は貯蔵等に必要な機械、器具、容器等が十分備わっていることと、製造場が工場立地法、下水道法、水質汚濁防止法、食品衛生法等製造場の設備に関する法令等に抵触していないこと
他の法令で許可等が必要な場合もあります。
当事務所では全くの未経験の方の酒類製造のご支援等も行っております。酒類の製造業をご検討の方は、ぜひ一度ご相談ください。

ウィスキーやブランデー、梅酒を輸出する免許
ウィスキーやブランデー、梅酒、ワイン等を輸出される場合、必要な免許は、
・全酒類卸売業免許
・洋酒卸売業免許
・輸出酒類卸売業免許
・自己商標酒類卸売業免許
になります。
全酒類卸売業免許と自己商標酒類卸売業免許については、こちらを参照してください。
洋酒卸売業免許について
洋酒卸売業免許に関しては、国内卸売と輸出については、ウィスキーやブランデー、ワイン、梅酒などのリキュール、発泡酒等は輸出することもできます。
洋酒に該当する酒類に関しては、国産のもの、海外産のものにかぎらず輸出することができる免許になりますから、すでに洋酒卸売業免許を取得されている方は、日本酒や焼酎などを輸出するということのない限り、あらたに輸出酒類卸売業免許を取得する必要はありません。
この洋酒卸売業免許取得に関して、申請前に仕入先と予定販売先をある程度確定しておかなければならない他、下記の経験条件も必要となります。※地域によって異なります。
・酒類の製造、販売に直接従事した経験が3年以上 または
・調味食品等の販売業経営経験3年以上
・上記経験がない場合には、その他の事業経営経験と酒類販売管理研修の受講など必要となります。
が必要となってきますので、輸出酒類卸売業免許よりも取得条件は難しくなってきます。
輸出酒類卸売業免許について
この輸出酒類卸売業免許については、輸出に関しては、仕入れる予定の酒類は申請によりすべて取り扱うことができる免許になります。
申請の際に、日本酒や焼酎、ウィスキーやブランデー、梅酒等の仕入予定と販売予定があれば、それらを販売することができる輸出酒類卸売業免許が取得できます。
この免許取得に必要な条件は、
・今まで輸出等貿易に関する事業を行ったことがあるか または
・資料等により輸出することが確実であると認められるか
・輸出するための所要資金が十分にあるか(年間販売数量の2ヶ月分以上の仕入資金)
が必要になります。
ウィスキーやブランデー、梅酒等を輸出するために、これから新規で取得されるのであれば輸出酒類卸売業免許を取得し、すでに洋酒卸売業免許を取得されている方は、新たに免許取得する必要もありません。

お酒の値段はどうやって決まる?
これからお酒の販売ビジネスを始めたいという方にとって、免許申請や店舗の確保などやるべきことは数多くあります。開業に関連するお悩みを聞かせていただく中で、価格設定に関するお話をうかがう機会も少なくありません。こちらでは販売価格がどうやって決定するのかをご紹介します。
お酒が消費者の手元に届くまで
お酒の価格を決定する上で、消費者の手元に届くまでの流通過程は大事な要素となります。
例えば店舗で取り扱う場合、蔵元・メーカー(生産者)→問屋・卸売業者→小売店・酒屋・量販店→消費者・飲食店という大まかな流れが考えられます。生産者はまず問屋などに卸す際に標準価格で販売しますが、消費者が支払う価格には流通過程で業者が取るマージンがプラスされています。
また、免許を申請される際には、どの段階で販売するかによって取得すべき免許が異なることにも注意が必要です。
お酒の価格を決定する要素
それでは個々の銘柄による金額はどのように違うのでしょうか。標準小売価格以外に考えられる要素として、希少性からくるプレミア価格が挙げられます。例えば、同じ日本酒でも生産数の少ない人気銘柄の大吟醸と大手メーカーが大量生産するテーブル清酒であれば必然的に供給量が少ないほうが高額となります。
また、ワインであれば生産地やワイナリーごとの格付や作り手がかけた手間暇、高名な評論家による評価によって価格が大きく変動することも珍しくありません。
お酒にかかる税金
お酒にかかる税金は主に酒税・消費税などが挙げられます。また、海外から輸入、もしくは日本から海外に輸出して販売する際には関税をプラスして価格を決定する必要が出てきます。酒税は分類によって税率が異なり、関税は日本と輸入元・輸出先となる国とでどのような取り決めがなされているかによって変わります。
例えば、日本でもチリワインをリーズナブルに楽しめるようになりましたが、その背景には日本とチリで自由貿易協定が結ばれたためチリワインの輸入にかかる関税が無くなったからという理由があります。こうした経済の流れを踏まえて、お酒の輸出ビジネスをご検討される方や免許取得を考える方も増えています。
(さらに…)

一般小売と通信販売の違いとは
通販の場合、自宅や会社の一室で事業を始められますが、小売店での販売となると店舗を借りなければなりません。店舗を借りたとしても、商品を陳列する棚を設置したり、冷蔵庫の設置や内装工事も必要になったり、開業までかなりのコストがかかります。
また、小売店での販売となると、ターゲットとなるお客様は店舗周辺の地元の方や店舗周辺の飲食店になるでしょう。配達もするなら、配達が可能な範囲内が顧客となります。しかし、通販なら、日本全国の人をターゲットとして事業が始められます。ターゲットとなる範囲が広がれば、それだけ多くの売上が期待できるのではないでしょうか。
通販で取り扱いできるお酒
しかし、通販ですべてのお酒を販売できるわけではありません。輸入酒には制限はありませんが、国産のお酒の場合、課税移出数量が3,000キロリットル未満である製造者が製造販売しているお酒に限られています。課税移出数量とは、製造場から持ち出されたお酒のうち、酒税の課税対象となるお酒の量をいいます。
大手メーカーが製造するお酒は、この数値を大きく上回るので通販で取り扱うことができませんが、地酒や地ビールなどは数値を上回ることはないので、通販で取り扱うことができます。
(さらに…)

海外のお酒を輸入販売するためには
ビール、ワインやブランデー、リキュールなど、海外には魅力的なお酒がたくさんあります。海外のお酒を輸入して日本国内で販売するためには、様々な手続きや準備が必要です。
お酒を輸入するとき
海外からお酒を輸入するときは、食品衛生法に基づいて「食品等輸入届出書」という書類を検疫所に提出しなければなりません。
また、必要に応じて、衛生証明書や試験成績書、原材料や成分、製造工程に関する説明書なども提出することがあります。必要書類を提出して審査や検査を受けますが、ここでは、指定外の添加物が含まれていないか、添加物の量が基準内であるか、といったことがチェックされます。
ラベルの作成が必要
お酒を輸入したら、ラベルを用意しなければなりません。お酒の表示については、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」でも定められていますが、お酒を製造した会社や製造場、酒類の分類、アルコール分、容量などの表示事項を記載したラベルをお酒の容器に貼ることになっています。これは、国産のお酒に限らず輸入したお酒についても同様で、輸入した人がラベルを用意することになっています。
お酒を販売するためには
酒類を輸入して販売するためには、酒販免許申請を行わなければなりません。酒類の販売業免許は主に酒類小売業免許と酒類卸売業免許があり、さらに販売方法やお酒の範囲によって、一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許、輸入酒類卸売業免許など細かく分けられます。
海外からお酒を輸入したとしても、免許がなければ販売できません。 (さらに…)

酒販免許を取得して実現する販売方法
「近い将来、絶対に自分の店をオープンさせる!」という夢を持ち、ひとつひとつ準備を進めている方もいらっしゃるでしょう。販売する品目の中に酒類がある場合は「酒販免許」を取得する必要がありますが、それによって次のような販売方法が実現します。
既存のお店でお酒販売を始めたい
現在取り扱っている商品が、お酒とよく合う食品だった場合、必然的にお酒の販売も検討するのではないでしょうか.。
たとえば、チーズ専門店が更なる売上向上を目指す場合。チーズに合うワインを独自の組合せで提案し、そのワインを同時に購入することができるようになれば、売上向上が図れます。
また、お土産屋さんや地元にちなんだ商品展開をしているお店でしたら、地元の地ビールや地酒の販売ができると、さらに集客率が高まる可能性もあります。地元限定のお酒や、珍しいお酒をラインナップすることで、他店との差別化を図ることができます。
飲食店と兼業でお酒を販売する場合
素材や料理へのこだわりを追求している飲食店の中には、料理に合わせたオリジナルのお酒を作っているところもあります。そのお酒の評判がよく、商品化を検討する場合、今までには必要のなかった酒販免許(酒類製造業免許、酒類販売業免許)が必要となります。原則飲食店は酒販免許の取得が難しいですが、飲食スペースと販売スペースを分けるなど、さまざまな要件を満たし、酒販免許を取得することが可能ですので、ぜひご相談ください。
お酒コレクターからセレクトショップのオーナーに転身する
希少なお酒や年代物のお酒は、コレクターにとって宝石と同じような価値があります。
これまでコレクションしてきたお酒を販売する専門店をオープンさせ、コレクターからオーナーへと転身したいとお考えの方もいらっしゃるでしょう。実店舗販売・通販いずれの場合にも、正規の申請・手続きでの酒販免許取得が必要となります。
商品の特徴や販売状況によって取得する必要のある酒販免許も違いますので、商品化を具体的且つ効率的に進めるためには、酒販免許取得に特化した行政書士への相談で的確なアドバイスを得ることが大切です。
当事務所は、開業当初より将来の利益を考えた酒販免許申請に特化し、スピーディーな対応で全国申請件数No.1の実績を誇る行政書士事務所です。
申請をお急ぎの方・酒販に関するトータルサポートをご希望の方・申請を断られたことがある方など、酒類販売をするお店をオープンさせるという夢を実現させるために、ぜひ当事務所にご相談ください。

酒類販売業免許申請・取得の難しさ
お酒は様々な嗜好品の中でも多くの方から支持されています。食文化とも深い関係性があり、和食・中華・韓国料理・イタリアン・フレンチなど食事に合わせて楽しみながら味わえるので、酒類販売ビジネスはこれからも需要が高まると予測できます。
しかし、アルコール飲料ですので適切な判断による販売が必要不可欠となります。
そのため、お酒を販売するには「酒類販売業免許」の資格取得が必須となっております。
こちらでは、酒類販売業免許申請・取得の難しさについてご紹介します。
必要な要件が細かく定められている
酒類販売免許と一口に言っても、小売、卸売、通販などの販売形態、販売先によって要件が異なります。
その他にも様々な観点から細かく要件が定められています。その一つひとつを厳密な審査基準により選定していくので、審査をクリアするためにはしっかりとした事前確認が必要なのです。
そのため、販売予定地を管轄している税務署に問い合わせて確認しようとしても、一人ひとりの販売に関する状況を細かくチェックして把握しなければ分からないことなので、明確な答えはもらえない場合が多いです。
正しい法令知識や対話力が必要
厳しい審査の中では、審査を担当している方から追加資料の提出を求められたり質問される場合もあります。とくに、免許要件を例外規定に該当する申請書を作成した場合には質疑の可能性が高くなります。
そんな状況でもすぐに審査員を納得させられる答えが出せるように、酒税法などの正しい知識と説得力のある対話スキルが必要となるのです。
酒類販売業免許を取得しても気をつけるべきこと
免許を取得しても安心はできません。様々な販売形態による免許の種類がありますので、自分が所有している免許条件に記載のないお酒や販売方法で販売すると違反となり一年以下の懲役又は50万円の罰金(酒税法58条)が科せられる場合もあります。一度免許を取得すると更新は不要ですが、小売業であれば3年に1度、酒類販売管理者研修に参加するようにしなければなりません。
また毎年4月に酒類販売数量報告の提出が必要となり、酒類受払帳の記帳義務もあります。
何か変更等あれば異動申告書の提出も必要となる場合もあります。
このように酒類販売業者となってからの手続きも様々ありますので、ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
このように酒類販売業免許申請は非常に大変で、個人ではなかなか免許申請、取得は難しいと思います。
そこで、酒類販売業免許申請を専門に対応している当事務所にお任せ頂ければ、開業準備やサイト運営などで忙しいお客様の代わりに時間や手間のかかる酒類販売業免許申請をスピーディーに対応させていただきます。

酒類販売免許取得時に知りたいお酒の定義
酒類販売業免許の取得を考えた時、酒税法上にお酒がどのような取り扱いになるのかは知っておきたい基礎知識の1つです。
こちらでは酒税法上のお酒の定義や分類についてご紹介します。
お酒とは?
お酒の分類は製造方法による分類と酒税法上の取り決めによる分類があります。「酒税法」では、「アルコール分1度以上の飲料」がお酒と定義されています。
その中には水などで薄めて飲む濃縮タイプや、粉末状の素を水で溶かしてアルコール分1度以上になるものを含みます。また、飲む以外の用途で使用するアルコール分1度以上のものや薬事法の規定を受けるアルコール分1度以上の医薬品・医薬部外品は除外されるため、酒類販売業免許の取り扱い範囲から外れます。
2種類の分類法
《製造方法による分類》
醸造酒…日本酒、ビール、ワイン、シードル
蒸留酒…焼酎、泡盛、ウィスキー、ブランデー、ウォッカ、ジン、ラム
混成酒…ベルモット、リキュール、みりん、合成清酒
《酒税法による分類》
酒税法によるお酒は4分類に分けられます。
発泡性酒類…ビール、発泡酒、その他
醸造酒類…清酒、果実酒など
蒸留酒類…連続式・単式蒸留焼酎、ウィスキー、ブランデー、原料用アルコール、スピリッツ
混成酒類…合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール、粉末酒、雑酒
販売する際は各種アルコール度数や原料、製造方法など詳細な定義があることに注意が必要です。
分類によって税額が異なる
酒類販売免許取得をご検討になる多くの方が気にされるのが、お酒にかかる税金です。
酒税法では、お酒の種類によって異なる税額が取り決められています。1キロリットルあたりの重量で税額が設定されますが、分類によって基本税率もしくは特別税率のいずれかが適用されます。特別税率はお酒の種類・アルコール度数・製造方法によって変わります。
(さらに…)

東アジアに向けた日本酒輸出ビジネス
酒類販売免許のご相談と合わせて日本酒輸出ビジネスに関するご相談も増えていますが、日本酒の輸出を考えた時に決して見逃せないのが韓国や台湾、香港、中国などの近隣諸国です。
日本酒需要の高い東アジア
現在世界各国に輸出されている日本酒の中でも、特に韓国・台湾・香港・中国といった東アジア近隣諸国からの需要は特に高いです。震災の影響で動きが鈍化した時期はあったものの、全体の流れを見ると現在でも需要は増加し続けています。どのようなお酒がどのような場所で需要を伸ばしているのかは各国で違うため、酒類販売免許申請の手続きをする前に各国の市場動向をチェックしておきたいところです。
各国の傾向
《韓国》
韓国は酒類の輸出金額ではアメリカに次いで2位となっています。国税庁の調査によれば2007年には4億6500万円だった輸出額が2012年には12億400万円と約3倍と著しい伸びを見せている国です。日本式レストランでの消費が主ですが、スーパーマーケットや量販店、コンビニでの販売も増加傾向にあります。しかし、通販・宅配が禁止されていることに注意が必要です。
《台湾》
安定した日本酒人気により確実な需要が見込めるエリアです。台湾内に流通する日本酒のほとんどは日本から輸出されたもので、最近では良質でブランド力の高い純米大吟醸も人気です。百貨店や専門店での取り扱いも多く販売価格も高い高級品が好まれますが、リーズナブルな日本酒を求める声が増えていることから今後新たな展開も期待できます。
《香港》
日本酒の輸出増加の一端を担う地域の1つです。2007年には7億600万円だった輸出額が2012年には14億9500万円とほぼ倍になっています。日本食レストランでの取り扱いが主で、各国に比べて取り扱い銘柄が格段に多いのもならではといった特徴です。また、香港は消費者保護のため、ラベル表示に規定があります。
《中国》
中国も日本酒の輸出量・輸出額ともに顕著な増加傾向にある国の1つです。主に日本食レストランで消費される傾向があり大手メーカによる中国産のものが人気ですが、高級志向のレストランでは日本産地酒の人気が高まっています。しかし、福島第一原子力発電所の事故を受けて、指定都県以外の道府県で製造された酒類であることの証明書を添付する必要があります。この証明書は国税局にて発行されます。
出典)「酒類の輸出統計」(国税庁) (http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/yushutsu/yushutsu_tokei/)
当事務所は酒類販売免許申請に特化しており、国内での酒類販売だけではなく東アジアを舞台とした酒類の輸出入でビジネスチャンスを掴みたいという方も、しっかりサポートします。

日本酒の輸出需要が高まっている理由
海外で日本酒の人気が出始め、日本酒輸出業者の需要も高まっています。それではなぜ日本酒の人気が高まっているのでしょうか?
海外で日本酒が人気の理由
今海外では和食ブームが大きな牽引力となり、日本酒も人気が高まりつつあります。
海外ではワインをはじめ、食事と一緒にお酒を楽しむ習慣が多く、和食と一緒に飲むものとして日本酒も注目を集めています。
また、日系スーパーで取り扱うお酒として日本酒を輸出する動きもあります。日系スーパーは日本からの移住者が多い国や地域で良く見かけるものですが、故郷の味を楽しみたい日系移民の方やそのご家族が代々日本酒を楽しんでいるようです。
日本酒が人気の国
日本酒はどのような国で人気なのでしょうか?
欧米アメリカやイギリス、オーストラリアでは和食ブームに後押しされて需要が高まっています。フランスやロシアもアメリカほどではありませんが安定した需要がある国です。
アジア各国香港、韓国、台湾、中国では元々日本酒=高級品というイメージがあり、富裕層がステータスとしてレストランで注文したり購入したりすることが多いです。
南米各国歴史的に日本から移住した方が多く、日本の食文化が溶け込んでいる地域もあり、このような国では日本食レストランも多いため、今後も需要があると見込まれています。
海外で楽しまれている日本酒はその土地の食文化に合わせて独自に発展していることもあります。
例えば、スパークリングタイプの日本酒が登場したり、洋風のおつまみと合わせて飲まれることも多いです。また、日本食でも人気の寿司店が増えていることも需要が高まっている理由の1つです。
大きなビジネスチャンスでもある
お酒の販売を始めようという方にとって、海外での需要の高まりは大きなビジネスチャンスとなるものではないでしょうか。
しかし、お酒の輸出は輸出先のマーケティングや販売先の確定、仕入先の蔵元との交渉、輸出酒類卸売業免許の取得などやるべき業務が多岐にわたります。輸出先のマーケティングや販売先の確定、免許申請が必要な場面では当事務所がお役に立てますのでお気軽にご相談ください。
(さらに…)

日本酒や焼酎を輸出できる免許
日本酒や焼酎などを輸出できる免許は、
・全酒類卸売業免許
・輸出酒類卸売業免許
・自己商標酒類卸売業免許
この3つになります。
全酒類卸売業免許について
この免許については、どんなお酒でもすべて国内卸売、海外卸売をすることができますが、
毎年、9月に各都道府県ごとに発表される免許件数の数件に対して、抽選で当選した申請者のみ取得することができます。
その倍率はかなり低いもの。
さらに、販売数量100キロリットルと定められているため、年間100キロリットルの2ヶ月分の仕入れ資金は必要となってきます。
輸出をするためだけに取得を考えられるのであれば、この全酒類卸売業免許は現実的ではありません。
輸出酒類卸売業免許について
輸出による販売方法でしか売ることができない免許にはなりますが、日本酒や焼酎、ウイスキーを輸出されるようでしたらこの免許が一番取りやすい免許となります。
また申請するにあたり、先に取り扱う予定酒類、仕入先と輸出先をある程度確定しておかなければなりません。
具体的には、仕入先との仮契約書、販売先との仮契約書が申請する際に必要になります。
この免許取得のためには、
・今まで輸出等貿易の経験があるか
・資料その他から輸出することが確実であると認められるか
などが条件となってきます。
少しわかりにくいですが、上記の条件について
現在の売上はどうなのか、役員の経営能力はどうなのか、輸出することについて明確なビジョンと手続きについて、スキームができているかどうかなど担当者によって細かくヒアリングされ、それらについて書面上に示さなければ申請ができません。
さらに、担当者(輸出免許に慣れていない)によっては、曖昧な通達内容から輸出免許について関係のないことを理由に申請できないと言われる方もいますが、輸出免許については通達例示規定により経験3年などという条件は付けられていないので、これから初めて輸出を行われる方でも申請できる可能性はあります。
その他には過去3期分の経営状況も免許取得条件に含まれてきます。
自己商標酒類卸売業免許について
この免許はその名前の通り、自らが開発した商標または銘柄の酒類を国内卸売、輸出ができる免許になります。
免許取得の前提として自ら開発した商標または銘柄の酒類がサンプルとしてでもよいので、あるかどうかが必要となってきます。
また輸出卸売業免許の条件にはない次の経験条件もあります。
・酒類の製造、販売業に直接従事した経験が3年以上 または
・調味食品等の販売業経営経験3年以上
・上記の経験がない場合にはその他の事業経営経験と酒類販売管理研修の受講など
などの条件が必要となってきますので、輸出酒類卸売業よりも取得するのが難しく、さらに輸出酒類卸売業で日本酒、焼酎、ウイスキーなどの販売免許取得できれば輸出に限ってはこの免許は必要ありません。
以上、これら3つの免許が日本酒や焼酎を輸出するために取得される免許ですが、現実的に取得しやすい免許としては輸出酒類卸売業免許だといえるでしょう。
ここからは確定していることではありませんが、
輸出に関して、その契約地が海外である場合、日本で仕入れをすることができる免許があれば、輸出ができるという解釈ができます。
なぜかというと、酒販免許を規定している酒税法はいわゆる国内法(日本国内においてのみ適用される法律)ですから、海外で契約をした場合、適用されるのはその販売される海外の法律になります。
つまり、このように酒税法は国内法だからという解釈だけでみると、一般酒類小売業免許などの小売免許だけであっても、海外の商社と海外で契約した場合、輸出することができるようです。税務署の判断としては、輸出先の国が輸出酒類卸売業免許でなければ取引できないなどの事業のない限り、一般酒類小売業免許でも問題ないようです。
今後、通達等で整備されていくとは思いますが、コンプライアンスを重視するのであれば、輸出酒類卸売業免許の取得はされたほうがよいでしょう。

米国を舞台にした日本酒輸出ビジネス
日本酒輸出ビジネスに挑戦したいとお考えの方に、米国での日本酒ブームやニーズを解説します。
米国での日本酒ブーム
世界各国でファンを増やしている日本酒の輸出額・輸出量は、ここ数年連続で過去最高を更新しています。
近隣国の中国・韓国・台湾への輸出を上回り、日本酒の輸出相手国トップとなっているのは米国です。
2008年のリーマンショックでは一時的な輸出の落ち込みが見られたものの、それ以降は年々増加傾向にあります。
「サキ(Sake)」と呼ばれていた日本酒も最近では「サケ」と正しい発音で浸透し、「ライスワイン」とお洒落に紹介されることもあります。これまではスタンダードな清酒の人気が定着していましたが、近年ではにごり酒・生酒・熱燗などを楽しむ人も増え、日本酒ブームは新しいステージに突入しています。米国の人々を魅了する日本酒の輸出は、ビジネスチャンスとして大きな可能性を秘めているのです。
州ごとのニーズの特徴
・ニューヨーク州
世界中から多くの人が集まるニューヨーク州では、バイヤーや愛飲家をターゲットにした試飲会やイベントが頻繁に開かれるなど、新しく珍しい日本酒への興味が大きいことが分かります。
日本食レストランの日本酒消費はマンハッタン周辺の限定的なエリアに集中しており、他店と差別化した個性的な日本酒を集客戦略のひとつとして取り揃える傾向があります。
・カリフォルニア州
日本食文化の浸透度と日本酒に対する認知度が他州よりも高く、日本酒市場として大きな魅力があるのは、日系移民による大きなコミュニティーが昔から存在しているカリフォルニア州です。
巨大な貿易港、多くの日本食レストラン、大規模な日系スーパーマーケット、大手日系食品商社本部などがあり、日本酒市場が活性化する要素が揃っています。
・ロサンゼルス
日本食レストランが広範囲で点在しているロサンゼルスでは、知名度が高く親しみのある商品が人気を得ている傾向があります。
日本酒輸出ビジネスにおける必要な免許申請や手続きをスムーズに進めて、大きなビジネスチャンスを掴みたいという方は当事務所へご相談ください。
輸出先のマーケティング・販売先の確定・仕入先との交渉・輸出酒類卸売業免許の取得など、多岐にわたるサポートで日本酒輸出ビジネスをサポートさせていただきます。

お酒の出張買取について
お酒の買取については、酒類販売業免許は必要ありません。さらに古物営業法でもお酒は古物には該当しません。
しかし、酒類販売業免許申請をする際には、出張買取をする場合には、当然適正に買い取りできるよう、お客様からの買取依頼から買取完了までの流れやそれに伴って必要となる書類をそろえなければなりません。
管轄の酒類指導官によっても、その取扱いは違いますが、具体的に必要とされる書類は、
・買取依頼から買取完了までのフロー図
・買い取るお酒に関する誓約書
・伝票類のサンプル
・酒類受払帳のサンプル
など、個々の事案によって内容やそろえる書類は変わりますが、適正に買い取ることができることを証明しなければなりません。
また、出張買取の場合でも同じ個人の方から継続的に買い取ることは無免許販売の助長とされる場合もありますので注意が必要です。

お酒の宅配買取について
お酒の宅配買取については、かなりの注意が必要です。
なぜなら、第三者(宅配業者)がお客様からお酒を受け取るため、本人確認等が間接的になるからです。
管轄の酒類指導官によって意見は異なりますが、あまりやって欲しくない買取方法なので、
申請は難しくなります。
宅配買取を行う前に、買取依頼をしたお客様に身分証明書のコピー等をもらい、
さらに誓約書にも署名押印してもらうことなど少し手間がかかる方法であれば可能かと思われます。
作成する書類に関しても個々の事案、担当する酒類指導官によって異なりますから、一概には言えませんが、
宅配買取フロー図、買取依頼をしたお客様の本人確認方法、誓約書、伝票等のサンプルなど必要となります。

お酒の輸出数量と金額(平成23年6月)
平 成 23 年 6 月 酒 類 の 輸 出 数 量 ・ 金 額
品 目 名
当 月 分
1 月 か ら の 累 計
前年同期
前年比
前年同期
前年比
L
千円
L
千円
L
%
千円
%
ビール
3,900,171
456,320
13,290,636
1,667,529
11,569,253
114.9
1,540,005
108.3
スパークリングワイン
270
541
3,006
1,561
3,835
78.4
2,498
62.5
その他のぶどう酒及びぶどう搾汁で
アルコール添加により発酵を止めた
もの
(2L以下の容器入りにしたもの)
33,099
12,702
125,245
178,863
65,439
191.4
76,371
234.2
その他のぶどう酒及びぶどう搾汁で
アルコール添加により発酵を止めた
もの
(2L超の容器入りにしたもの)
5,000
912
7,000
1,488
151
4,635.8
4,429
33.6
その他のぶどう搾汁
0
0
0
0
332
-
4,840
-
ベルモットその他のぶどう酒
(2L以下の容器入りにしたもの)
0
0
666
936
562
118.5
667
140.3
ベルモットその他のぶどう酒
(2L超の容器入りにしたもの)
0
0
0
0
0
-
0
-
清 酒
1,175,088
698,294
6,962,193
4,229,955
6,890,331
101.0
4,132,005
102.4
その他の発酵酒並びに発酵酒と
アルコールを含有しない飲料と
の混合物及び発酵酒の混合物
(他の項に該当するものを除く)
149,030
27,749
1,036,554
226,057
800,173
129.5
178,557
126.6
ぶどう酒又はぶどう酒もろみの
搾りかすから得た蒸留酒
3,659
2,305
22,144
101,469
21,233
104.3
64,431
157.5
ウイスキー
168,831
186,642
851,628
930,551
600,529
141.8
766,907
121.3
ラムその他これに類する発酵した
さとうきびの製品から得た蒸留酒
0
0
2,041
3,242
1,000
204.1
519
624.7
ジン及びジュネヴァ
371
309
673
561
0
-
0
-
ウオッカ
1,489
1,260
6,277
5,761
3,160
198.6
2,677
215.2
リキュール及びコーディアル
348,878
149,709
1,490,457
789,587
1,617,803
92.1
758,533
104.1
しょうちゅう
174,206
107,092
817,923
518,431
1,102,986
74.2
709,368
73.1
その他のアルコール飲料
105,669
29,397
589,895
165,223
1,437,699
41.0
191,980
86.1
合計
6,065,761
1,673,232
25,206,338
8,821,214
24,114,486
104.5
8,433,787
104.6
このようにほとんどのお酒が前年比を上回るなど、日本で製造されたお酒の輸出が増えてきています。
海外では日本酒が非常に人気です。

お酒の輸出数量上位20カ国(平成23年6月)
酒類の輸出数量上位20か国・地域(平成23年6月)
順位
国名
平成23年6月分
平成23年1~6月累計
数量
金額
数量
金額
前年同月比
前月比
前年同月比
前月比
輸出全体に
占める割合
輸出全体に
占める割合
KL
%
%
百万円
%
%
KL
%
百万円
%
1
大韓民国
2,051
173.4
192.8
317
158.5
202.3
7,534
29.9
1,385
15.7
2
台湾
1,538
145.0
307.2
254
124.5
193.1
4,235
16.8
1,019
11.6
3
アメリカ合衆国
897
129.1
132.2
419
106.9
102.8
4,113
16.3
2,341
26.5
4
香港
305
90.2
135.2
130
61.6
104.5
1,822
7.2
1,026
11.6
5
シンガポール
280
117.2
115.2
106
129.3
136.5
1,276
5.1
494
5.6
6
ロシア
152
50.3
96.9
37
52.1
108.4
1,155
4.6
270
3.1
7
オーストラリア
193
85.0
114.3
48
85.7
105.7
1,025
4.1
258
2.9
8
中華人民共和国
53
12.2
93.4
26
19.5
79.2
572
2.3
295
3.3
9
カナダ
130
224.1
273.0
38
200.0
287.1
455
1.8
145
1.6
10
パラオ
0
0.7
1.0
0
5.7
8.4
366
1.5
42
0.5
11
ベトナム
55
105.8
73.5
43
159.3
57.3
356
1.4
317
3.6
12
タイ
50
135.1
158.2
25
166.7
182.1
280
1.1
128
1.5
13
グアム
19
50.0
36.1
3
60.0
48.1
259
1.0
35
0.4
14
英国
51
141.7
174.5
70
166.7
194.4
253
1.0
284
3.2
15
ニュージーランド
54
108.0
262.4
13
118.2
423.0
218
0.9
47
0.5
16
ドイツ
25
166.7
139.0
16
123.1
214.8
177
0.7
77
0.9
17
マレーシア
45
140.6
349.7
32
290.9
235.7
149
0.6
123
1.4
18
フランス
34
81.0
143.8
40
125.0
153.3
148
0.6
189
2.1
19
イタリア
4
6.2
-
1
6.3
-
142
0.6
44
0.5
20
オランダ
40
190.5
324.6
17
242.9
289.4
133
0.5
62
0.7
上位20か国合計
5,976
119.5
173.1
1,636
104.8
134.7
24,669
97.9
8,584
97.3
輸出合計
6,066
119.0
171.3
1,673
104.2
132.9
25,206
100.0
8,821
100.0
※1財務省貿易統計(速報値)を元に作成されています。
※2順位は、平成23年1月~6月の累計輸出数量が多い順とされています。

コールセンターでお酒を販売するには
コールセンターでお酒を販売代行する場合、その販売内容にもよりますが、
酒類販売媒介業免許という免許が必要になります。
現在、この免許は大手が取得するケースが多く、あまり申請される方はいない免許になります。
なぜかというと、免許取得の条件がかなり厳しくなっているため、初めてお酒の販売をしようとする企業にとってはかなり高いハードルになっています。
必要とされる経験
免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に従業員として直接従事した期間が引き続き10年(これらの事業の経営者として直接業務に従事した者にあっては5年)以上である者
過去において酒類販売媒介業免許を取得し、相当期間経営したことがある者
酒類の副産物、原料、醸造機械等の販売業の業務に、従業員として直接従事した期間が引き続き10年以上である者
酒類の製造技術の指導等の経験を5年以上有している者
※これらの経験がない場合でも、その他の業種の経営経験や酒類販売管理研修受講、運営管理体制などで総合的に判断されます。経験がないからといってあきらめずぜひ一度ご相談ください。
必要とされる販売能力
申請者の年平均の取扱見込数量は100キロリットル以上であることが確実であり、継続して媒介業を行う見込みがある。
※酒類販売媒介業を継続して行う見込みがあると契約関係書類、他商品での実績等があればこの100キロリットル以上の媒介見込数量は不要です・
この酒類販売媒介業免許を取得希望される多くの方は、やはり経験要件が高い壁となっています。
申請先によっては個別判断してくれるところもありますが、あまり多く提出される申請ではないため、申請先担当者も経験がないケースもあり、
そのケースでは、この経営要件は満たしてもらう必要があります。
たとえ高い販売能力があったとしても、酒類の販売に関する知識がほとんど必要のない販売方法であっても、この酒類販売媒介業免許取得はかなり難しいものと言ってもよいでしょう。
私のもとにも媒介業に関して多くの相談が寄せられます。
ほとんどが媒介業免許が必要なのかどうかといった相談です。
それほど必要かどうかもわかりにくい免許になりますから、ぜひ一度ご相談ください。
お問い合わせフォームは24時間受付しております。お問い合わせフォームはこちら

ネット販売で取り扱うことのできるお酒について
インターネットで販売することができるお酒は限られています。
・国産のお酒であれば、販売しようとする酒類の範囲が、カタログ等の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である製造者が製造、販売する酒類
・輸入酒類
課税移出数量3000キロリットル未満のお酒とは、いわゆる地酒でどんなお酒がこれに該当するかについては製造元の蔵元がよく知っておられるかと思います。
この課税移出数量3000キロリットル未満のお酒を取り扱う場合、製造元のこれに該当するという証明書が必要となってきます。
この証明書ですが、製造元の蔵元に直接問い合わせをしてもらうとわかりますが、蔵元もこの証明書が通信販売酒類小売業免許申請に必要なことは十分承知していますので、酒類卸売業者(問屋)さんを通して取引をされる意思があるのであれば、酒類卸売業者(問屋)さんに言って証明書を取得されるか、酒類卸売業者(問屋)さんに製造元の蔵元を紹介してもらい証明書を発行してもらうかのどちらかになるかと思います。
これに対して輸入酒類ですが、初めて日本に輸入するお酒以外は特別な証明書などは必要ありません。
初めて輸入するお酒については、税関に製造工程表や成分分析表などを提出し、所定の手続をしなければなりません。
特に酒類の品目がハッキリしていない場合には、この税関の手続が終わらなければ申請は難しいでしょう。

フリマアプリでのお酒の販売について
スマホで簡単に販売ができるようになりました。
メルカリやラクマ、フリル、クルクル、プラットなどそういったフリマアプリでのお酒の販売についてですが、こういったアプリでお酒を継続的に販売する場合には、『通信販売酒類小売業免許』が必要となります。
またジモティーなど同一都道府県内を想定された取引の場合、同一都道府県内での販売であれば『一般酒類小売業免許』の取得で足りますが、多くの場合、他の都道府県への販売となると思われますので、『通信販売酒類小売業免許』の取得が必要です。
フリマアプリでこの『通信販売酒類小売業免許』の取得をする場合
必要な書類等としては、
・販売場の平面図、レイアウト図
・役員全員または個人の履歴書
・過去3期分の決算報告書等
・県税、市税等の納税証明書
・フリマアプリのサンプル画面
・国産酒を販売する場合、蔵元さんから課税移出数量3000kl未満の証明
などが必要となります。
その中でもフリマアプリのサンプル画面については、酒税法上必要な事項を盛り込まなければならないことや年齢確認の確実な実施等が必要となります。
副業として少量の販売でも『通信販売酒類小売業免許』が必要です
フリマアプリで副業として少量のお酒の販売でも、継続的に販売を行う場合には『通信販売酒類小売業免許』の取得が必要となります。
この継続的に販売を行うというのは、いらないものを処分する場合には該当しませんが、何度も販売を行う場合やあきらかに利益を得て販売を行う場合には、継続的に酒類の販売を行うことに該当します。
そのため、たとえ少しの量であってもお酒を出品する場合には、注意が必要となります。
お酒の無免許販売は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となりますし、副業の場合だと多くの方が税務申告されていないこともありますので、その場合は追徴課税等もありえるかもしれません。
これから先はインターネットでの販売よりもアプリでの販売が主流になるかもしれません。
実際にアプリでお酒を販売されようとしている方は、下記より今すぐご相談ください。
お問い合わせフォームは24時間受付しております。お問い合わせフォームはこちら

リサイクルショップでお酒を販売するためには酒販免許が必要
リサイクルショップでお酒の買取りのみを行うだけであれば酒類販売業免許は必要ありませんが、買い取ったお酒を販売するとなるとその販売方法による酒類販売業免許が必要となります。買い取ったお酒を店頭販売する場合には、一般酒類小売業免許、買い取ったお酒をオークションで販売する場合には、通信販売酒類小売業免許が必要となります。また同業者に販売をされる場合には酒類卸売業免許が必要となります。
酒類の買取販売が多く行われている現在でも、その申請は通常の申請と比べると難しいものだと言えます。
特に酒類卸売業免許申請は小売業免許申請と比べ、難易度は高いです。
税務署の担当酒類指導官によって判断の異なる点は、
仕入先が確実でなく、仕入れるお酒も特定できないこと
一般消費者(個人)からの買取りや処分品の回収など確実な仕入ではなく、販売するお酒も買取り状況によって異なること
同じ一般消費者(個人)から継続的にお酒を買い取ることができないこと
継続的にの判断は、各税務署によってその見解が異なりますが、同じ一般消費者(個人)から何度もお酒を買い取ることは、この一般消費者(個人)が継続的に酒類小売業者へお酒を販売することになるので酒類卸売業免許が必要となります。そのためリサイクルショップとしては無免許で酒類販売をすることを助長したことになるので、この買取りの体制づくりは、リサイクルショップでの酒類販売業免許申請の一番のポイントであると言えます。 (さらに…)

リサイクルショップの酒買取り
お酒の買取りだけであれば酒類販売業免許は必要ありません。
ただ、買い取ったお酒を販売しようとすると、酒類販売業免許が必要となります。
またリサイクルショップでは、酒税法では想定していない、一般消費者より仕入をすることになります。
そこで問題となってくるのは、
同じ人から継続的に買取をしていないか
どこかのお店で購入し、転売しているお酒ではないか
同じ人からの購入は、買取依頼に来られたお客さんが酒類卸売業免許を取得していない限り、継続的に買取依頼することは出来ません。たとえ、そのことを知らずに販売していたとしても無免許販売ということになりますから、未然にそうなることを防ぐ配慮が必要になります。 (さらに…)

ワインやリキュール、ビールなどを輸入するには
ワインやリキュール、ビールなどを輸入し、酒屋などの小売店に販売するためには、輸入酒類卸売業免許が必要になります。
また、日本にはじめてその酒類を輸入する場合には、その酒類の目的により、輸入しようとする酒類の成分分析表、製造工程表、食品等輸入届出書の提出が必要となります。
個人消費で輸入する場合には、そのような手続は必要ありませんが、その量は10キロ以下と制限されています。
試飲目的(サンプル)として輸入する場合
サンプルとして輸入する場合、輸入しようとする酒類の成分分析表、製造工程表、食品等輸入届出書の提出が必要となります。実際には、個人消費で輸入されてこうした届出等を事前に行うといった方法もありますが、一番手間のかからずコストもかからない方法としては、サンプル輸入されて、輸入品が届いたときに届出等を行う方法が一番良いでしょう。
販売目的で輸入する場合
輸入しようとする場所を管轄する検疫所へ酒類の成分分析表、製造工程表、食品等輸入届出書の提出が必要となります。
また輸入する際には、輸入酒類卸売業免許などの酒類販売業免許を取得していることも必要となります。
また、輸入酒類卸売業免許を申請される際に、仕入先(輸入元)と販売先(小売店)がある程度確定していなければなりませんので注意が必要です。
当事務所は酒類の輸入に関して多くの実績と万全のサポートを行っております。
今すぐお問い合わせください。
無料問い合わせフォームはこちら
フォームによるお問い合わせは24時間受付中

飲食店でお酒の小売をしたいと思ったら絶対知っておくべきこと
レストランやバーなどを経営していてお酒をテイクアウト販売したいと考えたことがある方は多いと思います。
「お酒を売ることに何か問題があるのでしょうか?」と思った方…実は酒税法により定められたルールを守らないと「売る」ことはできません。レストランやバーなどの飲食店では、お酒を「提供」しているのであって、基本的に「売る」ことはできないのです。お酒は国にとって税収の源です。また、この業界は小売業者、卸売業者、飲食店、一般消費者などが複雑になっているため、ルール作りが非常に大切なのです。この記事では、すでに飲食店を経営している方で、さらにお酒を販売しようと考えている方に、知っておくべきことについてご紹介しています。
飲食店でのお酒の小売も可能
ここで、飲食店でお酒を提供することと売ることの違いをご説明しておきましょう。飲食店でもビールやウイスキー、焼酎などのアルコールを飲むことはできますが、飲食店では酒類の栓は開けられた状態で出てきます。チューハイやハイボールも作られた状態で出てきます。これらはビンや缶がそのまま出てくることはありません。すなわち、お酒は提供されているのです。お酒を「売る」ことは、ビンや缶のまま、開栓せずに売ることを指します。そのため、通常はレストランやバーで「このウイスキー、おいしいし珍しいから宅飲み用に買いたい」と思っても、それは不可能です。売ってしまったらお店のオーナーは酒税法違反ということになります。
飲食業許可と酒類小売業免許
このように、飲食店では基本的にアルコールを売ることはできません。飲食店で必要なのは「飲食店営業許可」です。この許可を得ると、お客さんに料理や酒類を提供することが可能になります。一方、お酒の販売に必要なのは「一般酒類小売業免許」です。この免許が交付されると消費者に対してアルコールを小売できるようになります。一般酒類小売業免許で料理を出せないように、飲食店営業許可ではアルコールを売ることは原則できないのですが、これはあくまで原則です。
飲食店は原則酒販免許を取得できない?
あくまで原則というお話をしましたが、飲食店でも、条件次第で酒類小売業許可を取得することは可能です。免許制度の原則的な部分を守らなければならないこともあり、税務署では、飲食店での酒類小売について厳しい姿勢をとっているとも推測されます。飲食店で酒販免許を取得し、実際にお酒を販売するとなると、現在のお店のレイアウトを変える必要があるなど、面倒なことは確かですが、ビジネスの拡大や新展開を考えているのであれば、考えてみる価値は大いにあります。実際、ワイン販売コーナーを設けているレストランを見かけたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
飲食店でお酒の小売をする場合の準備
レストランやバーを経営していると、お客さんから宅飲み用にお酒を買いたいと尋ねられることがあります。高級で、しかも珍しいお酒が飲食店にあった場合、お客さんの心理を考えれば、その場で売ってしまいたいという気持ちになっても仕方ありません。しかし、それをやってしまうと違法になるので、飲食店で合法的にお酒の小売をするためには、まずは酒販免許を手に入れることが必要です。また、飲食店そのものやビジネスのやり方自体を変更する必要もあります。
場所を分割・完全に分割
酒販免許は酒類小売業免許と酒類卸売業免許に大きく分けられます。これだけでもわかるとおり、小売業を営む場合と卸売業を営む場合で別々の免許が必要なのです。飲食店が法に反してお酒を販売したり、風上に当たる卸売業者が一般消費者に直接お酒を販売したりしてしまうと酒販免許制度自体が崩壊してしまいます。原則的に飲食店はお酒を販売してはならないとされているのですが、これを可能にする分割という方法があります。つまり、お酒を販売する場所と飲食を提供する場所を完全に分けてしまうのです。
たとえばホテルにはレストランがありますが、ホテル内には酒類を売っているスペースがあります。レストラン内では販売できなくても、レストランとは別の場所で、お酒専用の販売場所を作れば販売は可能なのです。もちろん、条件はこれだけではありません。まだまだ分割する必要があるものはたくさんあります。
売上も分割する
お酒の売上が飲食の売上と同じレジで処理されることは認められないため、これらも分ける必要があります。完全にレジである必要はないのですが、酒販免許を申請する際にどんなレジを使用するのか、説明書や出力されるレシートについて説明する必要があるので、それらが可能なレジを選びましょう。
在庫も分ける
お酒の在庫も、提供用と販売用で分割しなければなりません。「一方が足りなくなったからちょっと拝借」というようなことが発生しないよう、在庫は厳重に管理する必要があります。
仕入れ先も分ける
飲食店で提供される酒類は通常、酒類小売業免許を持つ酒販店から仕入れます。しかし、飲食店が酒類小売業免許を取得してしまうと、これまでと同じ仕入先から酒類を仕入れることはできません。飲食店のすぐ風上に位置する酒販店を営むための免許を取得してしまうと、免許のシステム上、その風上に位置する業者からでないと仕入れることが不可能なためです。したがって、飲食店が新たに酒類小売業免許を取得すると、小売用のお酒に関しては新しいお酒の調達ルートを探す必要があります。ただし、いつも仕入れている酒販店が、卸売免許を持っている場合は、その業者から仕入れることが可能です。その際も、当然ながら飲食用と販売用で仕入を分割する必要があります。
角打ちについて
角打ち(かくうち)をご存じでしょうか。多くの場合、古くから営業している酒屋にある立ち飲み形式のスペースのことをこう呼びます。ここまで、飲食店と酒類販売業者は、その許可によりできること、できないことが決められていることを説明してきたのですが、この角打ちはこれまでの説明とは矛盾していそうです。この角打ちの営業形態は、飲食業と酒販業の狭間で営業している…こんな風にいえるかもしれません。このからくりについて理解すると、飲食店と酒販免許の関係についてもより深く理解できるようになります。
角打ちは場所が分かれていないのでは?
角打ちは、酒屋の中でお客さんが立ち飲みしているように見えます。はっきりと飲食スペースとお酒が売られているスペースにも区別がないように見えます。この状態の中でお客さんは平然と飲み食いしているのですが、問題はないのでしょうか。
実は、角打ちでは、飲食店のようにアルコールを提供しているのではなく、販売しています。お客さんにお酒を出すときは、そのお酒は開栓されていません。同様に、角打ちでは食べ物もオーダーすることができますが、調理されたものではなく、調理不要で食べられるものしか出されません。つまり、この角打ちではアルコールは販売されているものであり、食べ物も販売されているものをお客さんが買い、その場で食べている…こういう図式になっています。大げさに言えば、酒屋でお客さんが商品を買い、勝手にその場で食べている。これが角打ちです。
角打ちは、酒屋にとっては飲食店にお酒を販売するよりも高いマージンをとることができるのでうれしいですし、一般消費者から見れば、飲食店で飲むよりも安く飲めるわけで、いいことのようにも思えます。
角打ちの立ち位置は曖昧
しかし、角打ちのような販売手法は、免許制度の本来の姿を考えると、非常に曖昧な立ち位置にあることは間違いありません。先ほども触れたように、上流に位置する業者が安い値段で下流にいる業者や消費者に商品を流してしまうと、公正な取引や税収といった面で問題が発生します。
この営業形態を見ると、飲食業と酒販業を同時に行うことは、酒販免許の本来の姿を考えると望ましくないといえます。もちろん、ご紹介してきたようにすべてを分割することで飲食業と酒販業を同時に行うことは可能です。ただし、税務署側のチェックが厳しくなることにも覚悟する必要があります。
飲食店でお酒の小売をする場合の要点
飲食店でお酒の小売をする場合のチェック項目についてまとめてみました。
・スペースを完全に分割
お酒を販売する専用スペースを設けて、飲食の場所とは完全に分割します。
・伝票も分ける
納品伝票においても、飲食店用と販売用の酒類を分ける必要があります。
・会計も分ける
お酒と飲食は別々のレジで会計する必要があります。
・仕入帳簿も分ける
仕入帳簿も分けなければなりません。
・在庫も分ける
伝票が分かれているからといって、飲食店用と販売用をいっしょに保管することはできません。
飲食店で酒販免許を取得するなら専門家に相談を
このように、飲食店で酒販免許を取得するには、数々のポイントをクリアする必要があります。税務署も原則的にはこれらを両立することには厳しい立場をとっているため、やはり手続きにくわしい専門家に相談するのがはじめの一歩になります。酒販免許の専門家には、税務署にいる酒類指導官、もしくは酒販免許の手続きに詳しい行政書士がいます。飲食店での酒販免許取得は、専門家のサポートは欠かせません。
まとめ
飲食店を営みつつ、酒販免許を取得する際に知っておくべきことを、酒販免許の本来の目的や、角打ちの説明をしながら解説してきました。飲食店の酒販免許取得は、税務署も原則、認めていないように、なかなか難易度が高くなります。認められたとしても販売スペースから仕入、お酒の在庫管理まですべて分ける、新しい仕入れルートの開拓など、やるべきことは数多くあります。お近くの税務署、または酒販免許にくわしい当事務所にご相談ください。ご相談はこちらから

既存の会社で酒販免許をとりたい!と思ったら知っておきたいこと
新たなビジネス展開の一環として、酒類販売免許の取得を考えている会社の方は、ぜひこの記事を参考にしてください。現在、すでに営業中の会社が酒販免許を取得することは可能です。しかし、知っておくべきこと、準備するべきことはたくさんあります。条件が整っていないのに酒販免許の取得申請をしても、お金や時間を無駄にしてしまうだけなので、この記事でまずはポイントを押さえてください。
酒販免許は既存の会社で取得可能
会社の新たな事業展開のために酒販免許の取得を考えているという会社は数多くあります。実際、現在すでに営業中の会社で免許をとることは可能ですが、ハードルは低くはありません。これから酒販免許を取得するなら、最初にすべきことは専任のスタッフがいる税務署、もしくは酒販免許に詳しい当事務所に相談することですが、この記事では既存の会社にて酒販免許を取得する方法についての概要をご紹介していきます。
酒販免許取得の条件
酒販免許について取り仕切っているのは税務署です。税務署では、酒販免許を交付する条件を設定しています。さまざまな要件があるのですが、すでに営業している会社が免許を取得する場合は、以下の要件をかならずチェックされることになります。
決算書はかならずチェックされる
すでに営業している会社の場合は、これまでに決算を行っていますので、決算書がかならずチェックされます。たとえば赤字続きの会社で免許の取得申請をしても、交付される可能性はほとんどありません。つづいてこの決算書についての内容も含む、酒販免許取得条件について見ていきましょう。
税務署が定める取得条件
取得申請が可能な条件としては、以下のようなものがあげられます。
・自己破産により法的な処分を受けた過去(直近3年間)がない人
・直近の決算において、繰越損失が資本額を上回っていない会社
・直近3期のすべて決算において、損失が資本額の2割を上回っていない会社
大雑把ではありますが、これらの要件を満たしていれば、取得申請を行うことが可能です。つづいては、もう少し細かくこれらの要件について解説します。
人的要件
人的要件は、個人や経営者に求められるものです。直近3年間で禁固刑を受けている方などは、この人的要件を満たすことができないため、免許の取得申請を行うことはできません。
経営基礎要件
免許取得を申請しようとする経営者は、上で紹介している「自己破産により法的な処分を受けた過去がない人」であると同時に、経営について豊富な知識と経験を持っている必要があります。さまざまな要素がありますが、上でご紹介している「直近の決算において繰越損失が資本額を上回っていない会社」「直近3期の決算において、損失が資本額の2割を上回っていない会社」はまさにこの経営基礎要件に当たります。そのほか、「税金を滞納していない」「銀行との取引を制限されていない」などもこの要件に該当します。
経営についての知識や経験に関しては、過去に会社を経営していたというだけでは不十分です。過去に同種のビジネスを営んでいたり、酒販業界での業務を経験したりしている人がこれに該当します。ただ、この要件について、税務署は「人」ではなく「経営陣」の知識や経験を総合的に見て判断します。ひとりの経営者に酒販業界で働いた経験がなくても、ほかの経営者に業界経験があれば、クリアできると考えていいでしょう。誰も業界経験を持っていない場合は「酒類販売管理研修」を受けることで取得申請を行える可能性があります。しかし、税務署によっては厳しく審査されることもあります。現在の経営陣に業界経験がない場合は厳しい審査になりますので、専門家に相談する必要があります。
酒販免許取得の準備
ここまでで、酒類販売免許は誰でも取得できるものではないということがおわかりいただけたと思います。しかし、ここまでで条件をクリアしているようなら前途はかなり明るいといえます。ここからは酒販免許取得に向けた準備について解説していきます。
事業の目的
既存の会社が酒類販売免許の取得を申請する場合、事業目的の中に「酒類の販売」を追加する必要があります。(すでに入っているのなら必要ありません)
役員を選ぶ際の注意点
すでにご紹介した「経営基礎要件」があるため、経営者として適切な人物は限られます。とくに難しいのが「経験」の部分です。
申請者等は、経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人である。
(参考 製造免許等の要件:https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sake/2-07.htm)
とされています。
実際、このような経験や経歴を持つ人物はそれほど多くありません。もう少し詳しく説明すると、申請者は酒販業務に3年以上勤めた経験があるか、調味食品販売業を3年以上経営しているなどの必要があります。
これを補うのが「酒類販売管理研修」です。業界での経験を誰も持っていない場合は、この酒類販売管理研修を受講して申請資格を満たさなければなりません。もちろん、役員を招聘するという手もありますが、人材が少ないことを考えると、酒類販売管理研修により条件を満たすのが現実的でしょう。
ロケーション
店舗を持ってお酒を販売する場合は、当然ながらその店舗を確保する必要があります。会社と酒類を販売する店舗の住所は、同じでなくてもまったく問題ありません。小規模のビジネスであれば、自宅の一角でインターネットを使って販売する場合もあると思いますが、そのビジネスにマッチした酒販免許を取得して営業すれば、このような営業形態でもまったく問題ありません。ただし、注意が必要なのは飲食店です。すでに会社の事業目的の中に飲食店の経営が含まれていたり、実際に飲食店を営んでいたりする場合、そのロケーションでの免許申請は難しくなります。飲食店で酒類販売業を営むことは禁じられているのです。
また、店舗スペースを借りる際も注意が必要です。会社保有の物件であれば縛りはありませんが、賃貸となると規約があります。物件によっては事業を行うことが禁じられている場合もありますし、特定の事業のみに限定されている場合もあります。書面にて酒類販売が可能であることを証明する必要があるので、時間に余裕を持って準備しましょう。
酒販免許の種類
既存の会社が新規事業のために酒販免許を取得する際の要件や注意事項について解説してきました。ここまで酒販免許と一言で表してきましたが、実はその内容は細分化されていて、事業を行うためには、その事業にあった酒販免許を取得する必要があります。
まず酒販免許は、「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2つに大分されます。小売と卸売を同時に行うにはどちらも必要になるということです。
酒類小売業免許
酒類小売業免許は、一般消費者のほか、飲食店や工場などにお酒を小売りすることが可能な免許です。この酒類小売業免許は、さらに「一般酒類小売業免許」「通信販売酒類小売業免許」などに細分化されています。一般酒類小売業免許は、すべてのお酒を販売可能で、一般消費者や飲食店などに小売りが可能ですが、都府県の壁を越えて取引することはできません。これを行うためには通信販売酒類小売業免許が必要になります。この免許は、インターネットなどの手段で販売を行えますが、扱うことのできるお酒に制限があります。
酒類卸売業免許
酒類卸売業免許は、「全酒類卸売業免許」「洋酒卸売業免許」「ビール卸売業免許」「輸出入酒類卸売業免許」「自己商標酒類卸売業免許」「店頭酒類卸売業免許」などに細分化されています。これらの内、全酒類卸売業免許を取得することはかなり厳しい状況です。洋酒卸売業免許では、ウイスキーやワイン、ブランデー、スピリッツなどの卸売業を行うことができます。輸出入酒類卸売業免許を取得すると、海外からお酒を輸入して国内の業者に卸売したり、その逆に海外の業者にお酒を輸出、卸売することが可能になります。
自己商標酒類卸売業免許は自社で商標登録している名称を用いた酒類の卸売をすることができます。これは日本酒でもワインであってもどんなお酒でも構いません。
店頭酒類卸売業免許はどんなお酒でも卸売することが可能ですが、免許を取得した店頭だけでさらに会員にしか卸売することができない免許になります。
酒販免許の取得は専門としている行政書士に相談を
酒販免許の取得は、このようになかなか要件が厳しいのが現実です。新規事業として酒販免許取得を考えるのであれば、専門家に相談することが第一歩となるでしょう。酒販免許の専門家がいる税務署や、全国的にも酒販免許に強い当事務所に相談するのがおすすめです。
まとめ
既存ビジネスの新展開のために酒販免許を取得することは可能です。ただし、ここまでご説明してきたように、その要件はなかなか複雑です。これまでに酒販ビジネスに関わったことのないスタッフや経営陣ばかりでは、手続きを進めることも大変です。最初にやるべきことは、税務署、もしくは行政書士に相談して会社の財務状況や経営陣の人選についてのアドバイスをもらうことです。専門家にアドバイスしてもらうことで、実現可否もわかりますし、その先のさまざまな準備や手続きに関してもスムーズに行えるようになります。

既存の会社で酒販免許を取得するために知っておきたいこと
インターネットの普及により、ネットショップでお酒を買う方も増えています。ネットでお酒を販売するために酒販免許を取得しようという個人の方も増えているようです。また、最近ではこのお酒のネット販売や海外への輸出を新たなビジネスチャンスと考えている会社も多くあるようです。日本でお酒を販売する場合は、かならず酒販免許を取得しなければなりません。酒販免許は、さまざまな要件を満たして初めてとれるものですが、会社の状況を確認し、準備をしっかり行えば、異分野からであっても取得することは可能です。この記事では、酒販免許についてくわしく説明するとともに、酒販免許取得の条件や事前準備、頼りになる酒販免許のプロについてご紹介していきます。
酒販免許は会社の新規事業用でも取得できる
会社を新たに立ち上げる際に酒販免許を取得するケースが多くありますが、すでに営業している会社でまったく新しい事業を行うために酒販免許の取得を検討しているという会社も数多くあります。もちろん、このような場合でも酒販免許を申請し、取得することはできますが、税務署では取得要件を設けていて、これに適合した個人や法人でないと免許を取得することは不可能です。確実に免許を取得するためには、まずは税務署か行政書士に相談して、免許取得の実現可否や、取得するための道筋をはっきりさせましょう。
酒販免許とは
酒販免許(酒類販売業免許)とは、飲むことを目的とした度数1%以上のアルコールを販売するために必要な免許です。飲用のアルコールなので、これは一般的には「お酒」のことであり、医療で使用するようなアルコールは酒販免許の対象ではありません。お酒を販売するといっても、レストランやバーなどの飲食店でアルコールを出すことは「販売」ではないと定義されているので、このようなお店でお酒を出す場合は、酒販免許は不要です。ただ、酒販免許と一口で言うもののその内容は細かく分かれているので、これから始めようと考えているビジネスに適合した酒類の免許を取得する必要があります。
酒販免許の種類
酒販免許は、小売を行うための「酒類小売業免許」と、卸売を行うための「酒類卸売業免許」の2種類に大きく分けられます。そしてその中でさらに細分化されているので、この中から新たに始めるビジネスに適したものの取得申請を行います。
酒類小売業免許
・一般酒類小売業免許
一般酒類小売業免許は、消費者やレストラン、居酒屋などの飲食店、お酒を使用してお菓子を作る工場などを相手に小売販売が行える免許です。お酒ならなんでも販売することが可能ですが、カタログやインターネットを用いて販売しない場合には、他の都道府県でも販売が可能です。逆に言えば通信販売にあたるような都道府県の境界を越えて、カタログやホームページなどを用いて、配送により販売することはできません。新規事業でこれを行いたい場合は、通信販売酒類小売業免許を取得する必要があります。
・通信販売酒類小売業免許
インターネットやカタログを利用してお酒を販売するための免許です。都道府県の境界を越えてお酒を販売することができますが、販売できるアルコール飲料の種類が限定されるというデメリットもあります。輸入されたお酒、もしくは年間課税移出数量が3000キロリットル未満の国産アルコール飲料なら、この免許で取り扱い可能です。
酒類卸売業免許
・洋酒卸売業免許
洋酒卸売業免許は、ワインやウイスキーなどを国内の業者に卸売するために必要な免許です。
・輸出入酒類卸売業免許
輸出入酒類卸売業免許は、海外からお酒を輸入し日本の業者に卸売をしたり、日本で仕入れたお酒を輸出して海外の業者に販売したりするために必要な免許です。
・全酒類卸売業免許
これは、アルコール飲料ならなんでも卸売できる免許ですが、現在、この免許を手に入れることは年に1度の抽選により件数も少ないため、非常に難しくなっています。
・ビール卸売業免許
こちらも文字どおり、ビールを卸売するために必要な免許です。抽選により免許付与されますが、抽選申込者が少ないため取得できる可能性は十分にあります。
・その他
そのほかに、店頭販売酒類卸売業免許や自己商標酒類卸売業免許など、特別なニーズに対応するための卸売用の免許があります。
酒類販売代理業免許、酒類販売媒介業免許
その他に、酒類販売代理業免許、酒類販売媒介業免許というものもあります。酒類販売代理業免許は現在その取得は非常に難しくなっています。これは税務署側が免許付与しないようにしているためです。
酒類販売媒介業免許は、お酒の販売で「いわゆる競り売り」や「コールセンター」などが必要となる免許です。これは取得できますが、その審査に4ヶ月かかることや国税庁の審査もあることから、申請が非常に難しく、専門家と言っている人でも申請したことがない方がほとんどです。
酒販免許取得の条件
免許を取得するためには、税務署が定めているさまざまな要件をクリアする必要があります。国としても、税収が滞ってしまうのでは免許を与える意味がありませんので、この要件については申請する側もシビアに考えなければなりません。その中でも主なものが、「経営基礎要件」「人的要件」です。
経営基礎要件
免許の取得申請を行う場合、申請を行う者は、「自己破産により法的な処分を受けた過去(直近3年間)」がなく、経営や業界について豊かな知識と経験を持っていなければなりません。
直近の決算にて資本額を上回る繰越損失を出していたり、直近3期の決算で資本額の20%を超える損失を出していたりする場合は、免許を得ることはできません。そのほか、税金の滞納がある場合や、なんらかの理由で銀行との取引を制限されているなどの場合も取得することは不可能です。すでに営業している会社は、決算書の数字がかならずチェックされます。税務署の要件を満たすことができない会社に免許が交付されることは原則としてありません。過去に数回程度ですがこの条件を満たしていなくても免許交付されたケースはあります。
酒類業界での知識や経験もなかなかハードルの高い要件です。過去に業界でビジネスを行っていた、また実際に業界での業務に就いていた人ならこの要件はクリアできます。もちろん、この要件は経営者個人を見るのではなく、税務署も経営陣全体を見て判断しています。そのため、経営陣全体が業界に関するなんらかの知識や経験を持っているのであれば条件をクリアできる可能性は高いといえるでしょう。ただし、現実的にはなかなかこううまくいくことはないと思います。ましてや新規ビジネスのために酒販免許をとろうと考えている会社にとっては、かなり厳しい条件であることは間違いありません。知識や経験の面で要件をクリアすることが難しい場合は、「酒類販売管理研修」の受講で要件をカバーすることが一般的ですが、それにしても審査において有利な条件ではありません。このようなケースは、やはり専門家へ相談するのがベストです。
人的要件
免許を取得しようとする個人や経営者は、人的要件も満たす必要があります。未成年者は酒販免許を取得することは不可能ですし、禁固刑を受けている方も酒販免許を取得することはできません。
酒販免許申請のための準備
酒販免許にはさまざまな酒類があり、取得にも条件がある、ということについて説明してきました。ただ、ここまでの説明で「うちの会社は大丈夫そうだ」というのであれば、酒販免許が取得できる可能性は高いといえるでしょう。つづいては、免許申請のために準備すべき事柄についてご紹介します。
事業を行う目的
既存の会社が新たな事業のために免許の取得を申請する際は、すでに入っている場合を除き、事業目的として「酒類の販売」を入れる必要があります。一言入れるだけですが、大きな会社だとこれだけでもさまざまな部署の承認が必要な場合があるので、できるだけ早めに対応しておきましょう。
事業を行う場所
事業を行う場所は、ルールに反しない限り、基本的にはどこでも問題ありません。ただ、その「ルールに反しない」が重要なところではあります。まず、事業の目的として「飲食店の経営」を記載している会社は注意が必要です。なぜなら、酒販免許は基本、飲食店が取得できない免許だからです。申請する際は、この点について説明する必要があります。記載しているだけで予定がないのなら、削除してしまうのも方法のひとつです。
また、店舗やオフィスを借りる場合も注意が必要です。賃貸物件の中には事業用でないものも含まれていますので、物件探しをする際はかならず、酒類販売業を営むことを不動産業者に伝えたうえで探さなければなりません。申請時は酒類販売ができる場所であることを証明しなければならないので、早めに用意しておくといいでしょう。
酒販免許取得に際してはかならず専門家に相談を
このように要件が多く複雑な酒販免許取得までの道のり。この道のりを、自信を持って乗り切るには、専門家にサポートしてもらったほうがいいでしょう。既存会社の新規事業として酒販免許を取得するならなおさらです。
税務署
酒販免許に関しては、それぞれの国税の管内に「酒類指導官」がある税務署があります。酒類指導官はお酒に関する税の専門家で、免許取得についても相談可能です。相談の際は、事前にアポイントをとっておきましょう。
行政書士
行政書士は書類作成のプロですが、業務の幅が広いため、酒類販売業免許申請を専門として数多くの申請をしている行政書士は少ないです。当事務所は全国の酒類販売業免許申請を代行しており、申請を受理する側の酒類指導官とは異なり、申請を行う側に立ってアドバイスをします。まずはお問い合わせください。
まとめ
既存ビジネスであっても酒販免許をとってビジネスの新しい展開に役立てることは可能です。それほど楽な道のりでないことは確かですが、条件さえ満たしていれば免許はとれます。ただ、手続きを自分たちだけで行うことはなかなか難しいので、税務署や当事務所にサポートしてもらうのが現実的です。

ゾンビ免許(旧酒販免許)の取得方法
現在、取得できない酒販免許があります。免許条件が現在のように『酒類の販売は通信販売を除く小売に限る。』ではなく『酒類の販売は小売に限る。』などと記載されている免許になります。いわゆるゾンビ免許と呼ばれる免許ですが、もう新規免許取得はできません。
では、どのようにして取得したらいいのでしょうか。
1.法人を買収する。(個人事業から法人成りさせてから買収する。)2.吸収合併、新設合併する。
など想定されますが、買収する際に注意していただきたい事項として、今現在通信販売を行っているのかどうか確認してください。個人事業から法人成りされる際でもそうですが、現在通信販売を行っていない場合には『酒類の販売は通信販売を除く、小売に限る。』という条件になってしまい、旧酒類小売業免許は取得できません。そのため、合併の際でも同じように通信販売の実績を作ってから手続きを進めていくようにしましょう。
ではどのくらい実績があればよいのか・・・
こちらについては、税務署によって判断が異なりますが、次回の酒類販売数量報告までや通信販売実績が6ヶ月から1年くらいというのが多いです。※当事務所では最短で3か月の通販実績だけでゾンビ免許(旧酒販免許)取得したケースもあります。※この通販の実績は、現行の酒税法では通信販売できない課税移出数量3000kl以上の酒類の通信販売をして実績を作らなければなりません。
酒税法解釈通達の要件について
合併等に伴い、酒類販売業免許新規申請と同時に免許取得している会社の既存販売場の酒類販売業免許の取消申請を同時に提出する。
免許取得している会社の既存販売場と同じ場所で営業するように申請する。※特定の条件下で販売場を移転後に法人成り、合併させたこともあります。
免許取得している会社の既存販売場が1年以上酒類の販売を行っていないなど休業していないこと。
酒類販売業免許新規申請する存続会社が経営基礎要件を満たしていること。
これらを満たしていないと現在の酒税法上の販売条件になってしまいます。この合併等によって申請される場合には、申請に至る経緯や内容等について詳しく確認されます。
買収された際の手続
こちらは実際の案件ごとに異なるので、一概には言えませんが、
1.酒類販売業免許移転許可申請2.酒類販売業免許新規申請3.酒類販売業免許取消申請
他にも蔵置所設置報告書や異動申告書も必要な場合もあります。
また合併される場合には、その合併方法により手続きの流れは異なりますので、税務署へ旧酒販免許取得の意思を伝え、手続きを慎重に進めていく必要があります。
このような難しい手続は酒類免許を専門としているミライ行政書士法人にお任せください!
当事務所ではゾンビ免許(旧酒販免許)を売りたい方、買いたい方のマッチングも行っております。お問い合わせはこちら

競売り(オークション)での酒販免許
古美術商の場合、店頭販売や通信販売、リサイクル業者間取引以外に、競売り(オークション)での販売をされる方もいると思います。
競売りでの販売の場合、直接価格の決定をするわけではなく、業者間で競り合う形になりますが、取引自体は手数料を競売り業者へ支払い、直接販売することになりますから、必要な酒類の免許は卸売業免許になります。
※競売業者は酒類販売媒介業免許が必要です。
卸売業免許については、 (さらに…)

経験なしでの洋酒卸売業免許申請
洋酒卸売業免許の通達による経験要件
申請者(申請者が法人の場合はその役員)及び申請販売場の支配人が次に掲げる経歴を有する者で、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を 経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合は、原則として、この要件を満たすものとして取り扱うこととしています。
1.免許を受けようとする酒類の製造業の業務経験3年以上
2.免許を受けようとする酒類販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)業務経験3年以上
3.調味食品等の販売業の業務経営経験3年以上
4.酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者
5.酒類の製造業経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者
6.酒類の販売業経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者
このように例示規定されており、なかなか新規参入するのは難しいと思われます。
しかし、この規程は経営基礎要件の一部であくまで例示の規定。
見方を変えて判断すれば、税務署との交渉の余地はあるかと思います。 (さらに…)

古物商間のお酒の販売について
お酒を買取り、それを一般消費者に販売する場合には、店頭売り等であれば、一般酒類小売業免許が必要となり、通信販売で販売するためには、通信販売酒類小売業免許が必要となります。
お酒を店頭で買取り、インターネットオークションで販売することや店頭で買い取ったお酒を販売する免許申請は、増えてきています。
そのため、酒類販売業免許取得されているリサイクルショップが増え、リサイクルショップ間(古物商間)でのお酒の取引も増えてくるかと思われます
リサイクルショップ間(古物商間)でのお酒の取引をするためには、一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許を取得しているだけではできません。
そのような業者間取引でお酒を販売するためには、酒類卸売業免許が必要となります。
買取業者間で取引をするお酒の種類によって次のような酒類卸売業免許が必要となります。 (さらに…)

国税局及び酒類指導官設置税務署等一覧表(平成23年7月10日現在)
札幌国税局
〒060-0042 札幌市中央区大通西10丁目 札幌第二合同庁舎 電話番号011-231-5011(代表)
酒類指導官
設置税務署
担当税務署
郵便番号
所在地
電話番号
札幌北
札幌中、札幌南、札幌西、
札幌東、小樽、室蘭、
岩見沢、苫小牧、
倶知安、余市、浦河
001-0031
札幌市北区北31条西7丁目
3番1号
011-707-5111
函館
八雲、江差
040-0014
函館市中島町37番1号
0138-31-3171
旭川中
旭川東、留萌、稚内、名寄、
滝川、深川、富良野
078-8504
旭川市宮前通東4155番31
旭川合同庁舎
0166-90-1451
帯広
釧路、根室、十勝池田
080-0015
帯広市西5条南6丁目1番地
0155-24-2161
北見
網走、紋別
090-0018
北見市青葉町3番1号
0157-23-7151
仙台国税局
〒980-8430 仙台市青葉区本町3丁目3番1号 仙台合同庁舎 電話番号022-263-1111(代表)
酒類指導官
設置税務署
担当税務署
郵便番号
所在地
電話番号
青森
弘前、八戸、黒石、
五所川原、十和田、むつ
030-0861
青森市長島1丁目3番5号
青森第二合同庁舎
017-776-4241
盛岡
宮古、大船渡、水沢、花巻、
久慈、一関、釜石、二戸
020-8677
盛岡市本町通3丁目8番37号
019-622-6141
仙台北
仙台中、仙台南、石巻、
塩釜、大河原
980-8402
仙台市青葉区上杉1丁目1番1号
022-222-8121
古川
気仙沼、築館、佐沼
989-6185
大崎市古川旭6丁目2番15号
0229-22-1711
秋田南
秋田北、能代、横手、
大館、本荘、湯沢、大曲
010-8622
秋田市中通5丁目5番2号
018-832-4121
山形
米沢、新庄、寒河江、
村山、長井
990-8606
山形市大手町1番23号
023-622-1611
鶴岡
酒田
997-0033
鶴岡市泉町5番70号
0235-22-1401
福島
相馬、二本松
960-8620
福島市森合町16番6号
024-534-3121
会津若松
喜多方、田島
965-8686
会津若松市城前1番82号
0242-27-4311
郡山
いわき、白河、須賀川
963-8655
郡山市堂前町20番11号
024-932-2041
関東信越国税局
〒330-9719 さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館 電話番号048-600-3111(代表)
酒類指導官設置税務署
担当税務署
郵便番号
所在地
電話番号
水戸
日立、土浦、古河、
下館、竜ヶ崎、
太田、潮来
310-8666
水戸市北見町1番17号
029-231-4211
宇都宮
足利、栃木、佐野、
鹿沼、真岡、大田原、
氏家
320-8655
宇都宮市本町10番6号(仮庁舎)
028-621-2151
前橋
高崎、桐生、伊勢崎、
沼田、館林、藤岡、
富岡、中之条
371-8686
前橋市表町2丁目16番7号
027-224-4371
熊谷
川越、行田、秩父、
所沢、本庄、東松山
360-8620
熊谷市仲町41番地
048-521-2905
浦和
川口、西川口、大宮、
春日部、上尾、越谷、
朝霞
330-9590
さいたま市浦和区常盤4丁目11番19号
048-833-2651
新潟
新津、巻、新発田、
村上、佐渡
951-8685
新潟市中央区営所通二番町692番地の5
025-229-2151
長岡
三条、柏崎、小千谷、
十日町、糸魚川、高田
940-8654
長岡市千歳1丁目3番88号
長岡地方合同庁舎
0258-35-2070
長野
上田、信濃中野、佐久
380-8612
長野市西後町608番地の2
026-234-0111
松本
飯田、諏訪、伊那、
大町、木曽
390-8710
松本市城西2丁目1番20号
0263-32-2790
東京国税局
〒100-8102 千代田区大手町1丁目3番3号 大手町合同庁舎第3号館 電話番号03-3216-6811(代表)
酒類指導官設置税務署
担当税務署
郵便番号
所在地
電話番号
千葉東
千葉南、千葉西、
館山、木更津、茂原
260-8577
千葉市中央区祐光1丁目1番1号
043-225-6811
松戸
市川、船橋、柏
271-8533
松戸市小根本53番地の3
047-363-1171
成田
銚子、佐原、東金
286-8501
成田市加良部1丁目15番地
0476-28-5151
京橋
麹町、神田、日本橋、
小石川、本郷
104-8557
中央区新富2丁目6番1号
03-3552-1151
芝
麻布、品川、荏原、
大森、雪谷、蒲田
108-8401
港区芝5丁目8番1号
03-3455-0551
新宿
四谷、中野、杉並、
荻窪
169-8561
新宿区北新宿1丁目19番3号
03-3362-7151
東京上野
浅草、王子、荒川、
足立、西新井
110-8607
台東区池之端1丁目2番22号
上野合同庁舎
03-3821-9001
渋谷
目黒、世田谷、北沢、
玉川
150-8333
渋谷区宇田川町1番10号
渋谷地方合同庁舎
03-3463-9181
豊島
板橋、練馬東、練馬西
171-8521
豊島区西池袋3丁目33番22号
03-3984-2171
葛飾
本所、向島、江東西、
江東東、江戸川北、
江戸川南
124-8560
葛飾区立石8丁目31番6号
03-3691-0941
立川
八王子、武蔵野、青梅、
武蔵府中、町田、日野、
東村山
190-8565
立川市高松町2丁目26番12号
042-523-1181
横浜中
保土ヶ谷、横浜南、
戸塚、横須賀、鎌倉
231-8550
横浜市中区山下町37番地9号
横浜地方合同庁舎
045-651-1321
川崎北
鶴見、神奈川、緑、
川崎南、川崎西
213-8503
川崎市高津区久本2丁目4番3号
044-852-3221
厚木
平塚、藤沢、小田原、
相模原、大和
243-8577
厚木市水引1丁目10番7号
046-221-3261
甲府
鰍沢
400-8584
甲府市丸の内1丁目11番6号
055-233-3111
山梨
大月
405-8585
山梨市上神内川738番地
0553-22-1411
金沢国税局
〒920-8586 金沢市広坂2丁目2番60号 金沢広坂合同庁舎 電話番号076-231-2131(代表)
酒類指導官設置税務署
担当税務署
郵便番号
所在地
電話番号
富山
高岡、魚津、砺波
930-8530
富山市丸の内1丁目5番13号
富山丸の内合同庁舎
076-432-4191
金沢
七尾、小松、輪島、
松任
920-8505
金沢市西念3丁目4番1号
金沢駅西合同庁舎
076-261-3221
福井
敦賀、武生、小浜、
大野、三国
910-8566
福井市春山1丁目1番54号
福井春山合同庁舎
0776-23-2690
名古屋国税局
〒460-8520 名古屋市中区三の丸3丁目3番2号 名古屋国税総合庁舎 電話番号052-951-3511(代表)
酒類指導官設置税務署
担当税務署
郵便番号
所在地
電話番号
岐阜北
岐阜南、大垣、高山、
多治見、関、中津川
500-8711
岐阜市千石町1丁目4番地
058-262-6131
静岡
清水、島田、富士、
藤枝
420-8606
静岡市葵区追手町10番88号
054-252-8111
浜松西
浜松東、磐田、掛川
430-8585
浜松市中区中央1丁目12番4号
浜松合同庁舎
053-555-7111
沼津
熱海、三島、下田
410-8686
沼津市米山町3番30号
055-922-1560
名古屋中村
名古屋西、中川、
一宮、半田、津島
453-8686
名古屋市中村区太閤3丁目4番1号
052-451-1441
名古屋中
千種、名古屋東、名古屋北、
昭和、尾張瀬戸、小牧
460-8522
名古屋市中区三の丸3丁目3番2号
名古屋国税総合庁舎
052-962-3131
熱田
豊橋、岡崎、刈谷、
豊田、西尾、新城
456-8711
名古屋市熱田区花表町7番17号
052-881-1541
津
四日市、伊勢、松阪、
桑名、上野、
鈴鹿、尾鷲
514-8545
津市桜橋2丁目99番地
059-228-3131
大阪国税局
〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館 電話番号06-6941-5331(代表)
酒類指導官設置税務署
担当税務署
郵便番号
所在地
電話番号
大津
彦根、長浜、近江八幡、
草津、水口、今津
520-8510
大津市中央4丁目6番55号
077-524-1111
上京
左京、中京、東山、
下京、右京、園部
602-8555
京都市上京区一条通
西洞院東入元真如堂町358
075-441-9171
伏見
宇治
612-0084
京都市伏見区鑓屋町
075-641-5111
福知山
舞鶴、宮津、峰山、
豊岡、和田山、柏原
620-0055
福知山市篠尾新町1丁目37番地
0773-22-3121
東
大阪福島、西淀川、東成、
旭、城東、東淀川、北、
大淀、枚方、門真
540-8557
大阪市中央区大手前1丁目5番63号
大阪合同庁舎第3号館
06-6942-1101
南
西、港、天王寺、浪速、
生野、阿倍野、住吉、
東住吉、西成
542-8586
大阪市中央区谷町7丁目5番23号
06-6768-4881
堺
岸和田、泉大津、泉佐野
590-8550
堺市堺区南瓦町2番20号
072-238-5551
茨木
豊能、吹田
567-8565
茨木市上中条1丁目9番21号
072-623-1131
東大阪
八尾、富田林
577-8666
東大阪市永和2丁目3番8号
06-6724-0001
神戸
兵庫、長田、須磨、洲本
650-8511
神戸市中央区中山手通
2丁目2番20号
078-391-7161
姫路
相生、龍野
670-8543
姫路市北条1丁目250番地
079-282-1135
明石
加古川、西脇、三木、社
673-8555
明石市田町1丁目12番1号
078-921-2261
西宮
灘、尼崎、芦屋、伊丹
662-8585
西宮市江上町3番35号
0798-34-3930
奈良
葛城、桜井、吉野
630-8567
奈良市登大路町81
奈良合同庁舎
0742-26-1201
和歌山
海南、御坊、田辺、
新宮、粉河、湯浅
640-8520
和歌山市湊通丁北1丁目1
073-424-2131
広島国税局
〒730-8521 広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎1号館 電話番号082-221-9211(代表)
酒類指導官設置税務署
担当税務署
郵便番号
所在地
電話番号
鳥取
米子、倉吉
680-8541
鳥取市富安2丁目89番地4
鳥取第一地方合同庁舎
0857-22-2141
松江
浜田、出雲、益田、
石見大田、大東、西郷
690-8505
松江市向島町134番10
松江地方合同庁舎
0852-21-7711
岡山東
岡山西、西大寺、瀬戸、
児島、 倉敷、玉島、
津山、玉野、笠岡、
高梁、新見、久世
700-8655
岡山市北区天神町3番23号
086-225-3141
広島東
広島南、広島西、広島北、
三原、尾道、福山、府中、
三次、庄原、廿日市、吉田
730-0012
広島市中区上八丁堀3番19号
082-227-1155
西条
呉、竹原、海田
739-8615
東広島市西条昭和町16番8号
082-422-2191
山口
下関、宇部、萩、徳山、
防府、岩国、光、長門、
柳井、厚狭
753-8509
山口市中河原町6番16号
山口地方合同庁舎2号館
083-922-1340
高松国税局
〒760-0018 高松市天神前2番10号 高松国税総合庁舎 電話番号087-831-3111(代表)
酒類指導官設置税務署
担当税務署
郵便番号
所在地
電話番号
徳島
鳴門、阿南、川島、
脇町、池田
770-0847
徳島市幸町3丁目54番地
088-622-4131
高松
丸亀、坂出、観音寺、
長尾、土庄
760-0018
高松市天神前2番10号
高松国税総合庁舎
087-861-4121
松山
今治、宇和島、八幡浜、
新居浜、伊予西条、大洲、
伊予三島
790-0808
松山市若草町4番地3
松山若草合同庁舎
089-941-9121
高知
安芸、南国、須崎、
中村、伊野
780-0061
高知市栄田町2丁目2番10号
高知よさこい咲都合同庁舎
088-822-1123
福岡国税局
〒812-8547 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 福岡合同庁舎 電話番号092-411-0031(代表)
酒類指導官設置税務署
担当税務署
郵便番号
所在地
電話番号
小倉
門司、若松、
八幡、行橋
803-8602
北九州市小倉北区大手町13番17号
093-583-1331
博多
香椎、福岡、西福岡、
直方、飯塚、田川、
筑紫、壱岐、厳原
812-8706
福岡市東区馬出1丁目8番1号
092-641-8131
久留米
大牟田、甘木、
八女、大川
830-8688
久留米市諏訪野町2401の10
0942-32-4461
佐賀
唐津、鳥栖、
伊万里、武雄
840-8611
佐賀市駅前中央3丁目3番20号
佐賀第二合同庁舎
0952-32-7511
長崎
佐世保、島原、諫早、
福江、平戸
850-8678
長崎市松が枝町6番26号
095-822-4231
熊本国税局
〒860-8603 熊本市二の丸1番2号 熊本合同庁舎1号館 電話番号096-354-6171(代表)
酒類指導官設置税務署
担当税務署
郵便番号
所在地
電話番号
熊本西
熊本東、八代、人吉、
玉名、天草、山鹿、
菊池、宇土、阿蘇
860-8624
熊本市二の丸1番4号
096-355-1181
大分
別府、中津、日田、
佐伯、臼杵、竹田、
宇佐、三重
870-8616
大分市中島西1丁目1番32号
097-532-4171
宮崎
都城、延岡、日南、
小林、高鍋
880-8666
宮崎市広島1丁目10番1号
0985-29-2151
鹿児島
川内、鹿屋、出水、
指宿、種子島、知覧、
伊集院、加治木、大隅
890-8691
鹿児島市荒田1丁目24番4号
099-255-8111
大島
-
894-8677
奄美市名瀬長浜町1番1号
名瀬地方合同庁舎
0997-52-4321
沖縄国税事務所
〒900-8554 那覇市旭町9番地 沖縄国税総合庁舎 電話番号098-867-3601(代表)
酒類指導官設置税務署
担当税務署
郵便番号
所在地
電話番号
那覇
宮古島、石垣、
北那覇、名護、沖縄
900-8543
那覇市旭町9番地 沖縄国税総合庁舎
098-867-3101

自動販売機を申請する場合
現在、全国税務署では酒類の自動販売機を設置する申請は、新規では、許可が下りません。
たとえ、店舗の前に設置する場合でも、新規でも原則として許可をおろしていないようです
新規で酒類販売業免許申請をし、免許交付を受けてから自動販売機を設置する場合には、酒類販売管理者が管理できる状態であれば販売することができるようです。管理できる状態というのは、何かあればすぐに対応できる状態である必要があります。
例えば24時間自動販売機を稼働させるとすると、24時間いつでも酒類販売管理者がすぐに駆けつけることができ、連絡も取れる状態でなければなりません。
お酒の自動販売機を設置するというのは、税務署側も20歳未満の者の飲酒防止の観点からあまり許可したくないようですから、新たに自動販売機を設置する場合には、根気のいる申請になると思われます。

酒の代理購入について
メイン業務は酒類の販売ではないため、酒類販売業免許を取得せず、酒類を購入し、メインの業務の付随業務としてお客さんに酒類を販売することについてですが、たとえ酒類に利益をのせて販売していなくても、無免許販売となりえます。
酒税法上、継続的に酒類を販売するためには、酒販免許が必要となると記載されていますから、たとえ利益を取らず代理購入という方法で販売していたとしても、酒類を継続的に販売していると見られる場合があります。
その取引内容によっては、免許が不要なケースもありますが、現在酒類の代理購入をされている方は注意が必要となるでしょう。

酒税法上のお酒の種類
お酒は酒税法上、その製造方法や原料成分により細かく分類されております。
製造方法にもよって分かれているため、同じお酒であっても分類が異なる場合もあります。 (さらに…)

酒販業者のための容器包装リサイクル法
事業者の役割
事業者はその事業に用いた容器包装使用料・製造量に応じて、その容器包装のリサイクル義務があります。
そのリサイクルシステムについては、まず消費者が分別排出し、それを市町村が分別収集し、リサイクル事業者が再商品化します。
これにより、容器包装廃棄物の減量化、資源の有効活用に取り組んでいます。
なお、酒類業者の一定の基準を満たすものは特定事業者とされ、容器包装の再商品化義務が生じます。
(さらに…)

酒販免許申請の経験要件は管轄税務署によって判断が異なる
一般酒類小売業免許申請の手引と通信販売酒類小売業免許申請の手引、酒類卸売業免許申請の手引には、次のような経営基礎要件があります。
個人で申請する場合には、その代表者が、法人で申請する場合にはその役員または支店長等(登記された支配人)が、次のいずれかの経験があるかどうか。
お酒の蔵元または酒屋、酒卸売業者(薬用酒だけの販売を除く。)の受注、発注、納品等の業務に従事した経験が3年以上
調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者またはこれらの業務に従事した期間が通算して3年以上
酒類小売組合などの役職員として相当期間継続して勤務した者
お酒の蔵元または酒屋、酒卸売業者の経営者として3年以上
これはすべての酒類指導官は同じ扱いをしています。
担当ごとに判断が異なるのは、次の内容です。
なお、これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、
酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験
税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等
酒類の小売業を経営するのに十分な知識及び能力が備わっているかどうか実質的に審査されます。 (さらに…)

酒類卸売業免許の要件緩和等について
酒類卸売業免許について、平成24年9月1日より、法改正が行われます。
経営基礎要件の基準数量(年間平均販売見込数量)の緩和
新たな免許区分の追加
全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許の免許可能件数の計算方法の変更
全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許に関する申請等手続きの変更
経営基礎要件の基準数量の(年間平均販売見込数量)の緩和について (さらに…)

酒類販売管理研修について
1.酒類販売管理研修の趣旨・目的
酒類販売管理研修は、酒類販売管理者において、致酔性などを有する酒類の特性や酒類小売業者が遵守すべき関係法令の知識の向上を図ることにより、販売場における酒類の適正な販売管理の確保について、より実効性を高め ることを目的として実施されるものです。
酒類小売業者が各店舗ごとに酒類を販売する管理者として酒類販売管理者を選任しなければならず、その酒類販売管理者は酒類販売管理研修を受講する必要があります。
この酒類販売管理研修は、3年に1度受講しなければなりません。
また、免許申請の際にも『酒類販売のための知識の補完のために』酒類販売管理研修を受講しなければ申請できないケースもあります。
具体的には、酒類販売について全くの未経験でお酒の免許を取得しようとする場合など免許申請前に受講し、申請書の添付書類で要求される場合もあります。
この場合、受講する必要があるのは、申請者自身または法人であれば役員の方となります。
今まで申請代行してきたケースのそのほとんどが、役員の方や個人事業主の方に免許申請時または免許申請後の審査期間内に酒類販売管理研修を受講するように言われてきましたので、お酒の免許申請をご検討の方は、先に受講をご検討されるとよいかもしれません。
研修を行っているのは小売酒販組合などの団体で、実施している団体によって受講料は様々ですが、半日程度の研修で3000〜5000円程度の受講料です。また東京や大阪、名古屋などの都心では酒類販売管理研修をよく開催しているのですが、それ以外の地域では2〜3ヶ月に1回などあまり開催していませんので、近隣で開催される際には受講されることをおすすめします。
(さらに…)

酒類販売管理者について
1.酒類販売管理者の選任義務
酒類小売業者は、販売場ごとに、酒類小売業免許を受けた後遅滞なく、酒類の販売業務に従事する者で酒類販売管理研修を受講した者のうちから『酒類販売管理者』 を選任しなければなりません。
酒類小売業者の個人事業主、 法人であれば役員が自ら酒類販売業務に従事する場合には、酒類販売管理者になることができます。
※酒類販売管理者を選任しなかった場合には、免許の取り消しや50万円以下の罰金に処せられることになっています。
(さらに…)

酒類販売管理者は各店舗に1名必要です。
酒類を小売する場合、各店舗に1名は酒類販売管理者をおかなければなりません。
酒類販売管理者研修は義務化され、酒類販売管理者はその研修を受講した者から選任しなければならず、3年に1回は酒類販売管理研修を受講する必要があります。
また酒類販売管理研修の受講修了証と酒類販売管理者標章を酒類販売場に掲示しなければなりません。
最低1名の酒類販売管理者ですが、その管理者が休みや店舗から出なければならないときなどの不在の場合には、その酒類販売管理者に代わる責任者をあらかじめ選任する必要があり、その責任者は酒類販売管理研修を受講する必要はありませんが、酒類の販売に関する知識を補完する意味で受講しておくとよいかもしれません。
新規に酒類販売業免許申請をする場合、役員や個人事業主が酒類の販売に関する知識を補完する意味で申請前に受講しておくと通達で定められた経験が不足していても免許交付される場合もあります。
地域によっては一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許については、この酒類販売管理研修を受講していれば、免許申請に必要な経験を満たしていると判断される地域もありますし、今まで別の事業を行っていた経験と酒類販売管理研修の受講によって免許申請に必要な経験を満たしていると判断する地域もありますので、酒類販売業免許申請をご検討の方は、半日の研修になりますから受講してみてはいかがでしょうか。

酒類販売管理者研修実施団体
酒類販売管理者研修実施団体
研修実施地域
研修受講料金
(社)日本フランチャイズチェーン協会
全国的に開催
4,700円
会員は2,200円
日本チェーンストア協会
沖縄県を除く各都道府県で開催
4,000円
会員は2,000円
(社)日本ボランタリー・チェーン協会
沖縄県を除く各都道府県で開催
5,000円
会員は3,000円
(社)新日本スーパーマーケット協会
全国的に開催
5,100円
会員は3,300円
全国小売酒販組合中央会
全国的に開催
4,500円
組合員は2,500円など
各都道府県ごとの酒類販売管理者研修実施団体 (さらに…)

酒類販売業者の記帳義務
酒類の販売業者には、酒税法の規定により帳簿への記帳義務が課せられています。酒類販売業者がこれらの義務を履行しない場合には、10万円 以下の罰金または科料に処せられることとなっています。
※ここでいう『酒類の販売業者』とは、酒場、料理店、旅館等のいわゆる接客業者も含むこととされてい ます。
1.記帳すべき事項
(1)仕入れに関する事項
酒類の品目別および税率の適用区分別(アルコール分別などに)に、
仕入数量
仕入価格
仕入年月日
仕入先の住所および氏名または名称
(2)販売に関する事項
酒類の品目別および税率の適用区分別(アルコール分別などに)に、
販売数量
販売価格
販売年月日
販売先の住所および氏名または名称 (さらに…)

酒類販売業者の承認義務
酒類販売業者が次に掲げる行為を行おうとするときは、その販売場の所在地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
①酒類販売業者が酒類に水または酒類を混ぜようとする場合
(新たな酒類の製造となる場合を除く)
②アルコール含有物を連続式蒸留機または単式蒸留機により蒸留した酒類に砂糖等を加えたものに該当するしょうちゅうを木製の容器に貯蔵しようとするとき
※申請を受けた税務署長は、酒税の取締りまたは保全上特に必要があると認められる ときは承認を与えないことができる。
(さらに…)

酒類販売業者の申告義務
酒類販売業者は、次の事項について販売上等の所轄税務署長に申告等を行う必要があ ります。
【毎年度報告を要するもの】
・毎年度(4月1日から翌年3月31日)の酒類の品目別販売数量の合計数量および年度末(3月31日)の在庫数量を翌年度の4月30日までに申告しなければなりません。
【その都度、申告等を要 するもの】 (さらに…)

酒類販売媒介業免許の改正点
平成24年9月1日より、酒類販売媒介業の要件が緩和されます。
まず大きな改正点として経営基礎要件が緩和されます。
今までは年間販売見込数量が240㎘から100㎘に緩和されることになります。
※酒類販売媒介業を行うことが確実であると過去の実績や関係書類から明らかであれば、100klの年間取引見込数量は不要です。
酒類販売媒介業免許の基準数量(年平均取扱見込数量)については、原則廃止し、「予定している媒介業を継続して行う見込みがある者」か否かで取扱能力を判定します。ただし、年平均取扱見込数量が100kl 以上である者は、取扱能力を有している者として取り扱います。
今回の全酒類卸売業免許の年間販売見込数量の緩和に伴い、 上記のような取扱いとなります。
ただ、経験要件はそのままですから、取得するのが難しい免許であることには変わりはありません。 (さらに…)

新たに追加される酒類卸売業免許
平成24年9月1日の改正に伴い、新たに酒類卸売業免許が追加されます。
店頭販売酒類卸売業免許
店頭販売酒類卸売業免許とは、自己の会員である酒類販売業者に対し店頭において酒類を直接 引き渡し、当該酒類を会員が持ち帰る方法による酒類の卸売ができる酒類卸売業免許をいいます。 この酒類卸売業免許で卸売できる販売先は、住所及び氏名又は名称並びに酒類販売業者である ことを免許通知書等により確認した上で、会員として登録し管理している酒類販売業者に限られますので、会員登録していない酒類販売業者に対して卸売することはできません。また、卸売できる販売方法は、店頭において酒類を直接引き渡し、当該酒類を自己の会員が直接持ち帰る方法による卸売に限りますので、販売した酒類を配達する方法による卸売はできません。
(さらに…)

新会社で酒販免許をとろうと思ったら絶対に知っておきたいこと
これから新しく立ち上げる会社でも酒販免許は取得可能です。酒販免許を取得するには実績が必要だと考えている方も多いようですが、実際に酒販免許を新規で申請する会社の多くが新しい会社です。この記事では新会社設立時に酒販免許を取得するための準備や方法について解説しています。ポイントを押さえれば新しい会社でも酒販免許は問題なく取得できますので、ぜひ参考にしてください。
新会社でも酒販免許は取得可能
酒販免許は、正式には酒類販売業免許と呼ばれるもので、文字どおり、お酒を販売するために必要な免許です。この酒販免許にはいくつか種類があり、販売しようとしている業態やお酒の種類により、必要な免許が異なることに留意する必要があります。酒類免許はかなり細かく分類されているのですべてをご紹介することは避けますが、大雑把に分けると「酒類卸売業免許」と「酒類小売業免許」の2種類となります。その他酒類販売代理業免許、酒類販売媒介業免許もあります。
すでに存在している会社で、新たに酒販免許を取得しようとする場合、会社の財務状況が厳しくチェックされます。そのため、過去3期の赤字が大きい場合や直近期における繰越の赤字が大きいと、酒類免許を取得することは原則できません。その点、新しく立ち上げる会社の場合は、決算実績がないので、当然、この項目は審査されません。つまり酒販免許は、現在の資金や役員の経験が重要視されることになりますが、これまでずっと営業してきた実績のある会社よりも、過去の実績を審査されることがなく、その点だけで言えば新しく立ち上げる会社のほうが取得しやすいのです。
酒販免許取得のチェック事項
このように財務面のチェックがないため、新規で立ち上げる会社のほうが酒販免許取得において既存の会社よりもメリットがあることは確かです。しかし、ただ免許の取得申請をすれば取得できるというほど甘くはありません、免許をとるためには以下の要件が必要です。
事業計画がないと取得不可
先にご紹介したとおり、酒販免許には「酒類卸売業免許」と「酒類小売業免許」があります。酒類卸売業免許は、お酒の卸売業者、小売業者を対象とした免許です。一方、酒類小売業免許は、お酒を店頭で販売する業者のための免許で、さらに細かい分類のなかには、ネットショップなどを対象とした、幅広い地域に販売する業者のための免許もあります。すなわち、どのような形で事業を行うかによって必要な免許が異なるため、綿密に事業計画を立てる必要があるのです。このなかには販売計画(いくらで仕入れていくらで売るのか、どの程度の販売量を見込んでいるのかなど)も含まれます。これから始める商売をできるだけ詳細にイメージし、事業計画に落とし込んでいきましょう。
取得のための条件
財務チェックが入らないとはいえ、新規に立ち上げる会社の経営者には、それなりの条件が求められます。納税状況も当然チェックされ、過去に破産し、今なお復権していない場合は、酒販免許を取得することは不可能です。これは経営基礎要件と呼ばれるもので、酒販免許取得に限って問われる要件ではありません。酒販免許を取得するには、経営者となる人物に対する審査があることに留意しましょう。
そのほかに経営者は、酒類を販売するために必要な知識や経験を身に付けている必要があります。したがって、経営者がお酒に関してまったく素人では酒販免許を取得することはできません。免許取得前に、各地で開催される「酒類販売管理研修」を受講することで、これを満たすことができることもあります。
新会社で酒販免許を取得するための準備
ここからは、新会社を立ち上げて酒販免許を取得するための準備について説明していきます。ポイントを押さえて確実にステップを踏んでいくことで、確実に酒販免許を取得しましょう。
税務署か行政書士に相談
日本で酒類の販売について取り仕切っているのは税務署です。酒類販売業を営むことを決めたら、まず相談すべきは税務署です。税務署には酒類指導官という酒販の専門部署がありますので、ここに連絡をとって相談しましょう。
税務署を訪れる前に、できる限り細かく新事業について説明できるようにしていくと、相談はより有意義な時間になります。もちろんこの段階ではわからないことも多いはずですが、それは問題ありません。それを確認する機会が、この税務署での相談です。
ちなみにこのような事前相談は、税務署への相談だけではなく、当事務所に相談することも可能です。全国対応しておりますのでお気軽にご相談ください。ご相談はこちら
事業目的をはっきりさせる
酒販免許を新しく立ち上げる会社で取得するには、事業目的をはっきりさせる必要があります。これはどんな事業を立ち上げる場合でも共通することです。具体的にいうと、新会社の事業目的の項目に、酒類販売に関する記載をしなくてはなりません。たとえば、「酒類の販売」などのように記載します。
事業目的の記載では注意しなければならない点もあります。もしも飲食店の経営も同時に考えているのであれば、事業目的にこれも盛り込まなければなりません。しかし、酒販免許を飲食店がとることは、お酒の仕入れルートの管理なども事業計画に盛り込まなければなりません。「やる予定はないが一応入れておこう」程度の場合は事業目的には含めないようにしましょう。また、この点について指摘されたら、「今はやらない」と答えておきましょう。
役員構成
会社には経営陣が必要となりますので、役員を決めなければなりません。すでにご紹介したとおりですが、経営陣には、実際にビジネスを運営した経験があること、そして酒販業界における経験、知識などが要求されます。これらは役員のうち1名だけ経験や知識があればよく、もし業界経験がない場合は、前出の酒類販売管理研修を受けることで業界経験として判断される場合もありますが、「必要最低限」という判断になります。
また、フランチャイズで始めようとする場合には、本部である会社が経験や実績があるかどうかにより判断されます。
新会社の場所
酒類販売免許を取得する住所と新しい会社の登記場所は、同じ場所でも別の場所でも問題ありません。ただし、免許の取得場所はかなり重要な要素なので、熟慮する必要があります。この点については、税務署や行政書士事務所に相談して、どのような場所に設定すればいいのか確認しておきましょう。具体的には、建物所有者だけでなく土地の所有者にも酒類の販売を行うことについて承諾をもらっておかなければなりません。
届出
これは新会社を設立したら必ず必要になる作業です。会社の住所地の役所、税務署、県税事務所などへ、会社の設立を届け出る必要があります。酒類販売免許の取得には納税証明書が必要となりますので、これを忘れると免許の取得申請ができません。
酒販免許取得が難しいケース
新会社を立ち上げて酒販免許を取得しようと考えても、条件によっては難しいケースもあります。既存の会社のように財務状況をチェックされることはないとはいえ、やはりお金に関するチェックは新会社の場合でも当然あります。ここからは、酒販免許取得を難しくする要素についてご紹介していきます。
まずは資本金額です。会社設立に際し、資本金額の規定はとくにありません。酒販免許取得を考えるなら「2ヶ月分の仕入資金」という基準がありますので、あまりにも少ないと資金の調達が必要となります。これには国税庁が定めている企業の財産要件が関わっています。この財産要件は、既存の会社が酒販免許を取得する際にも適用されるもので、「販売能力及び所要資金等の検討」という項目にある、
・最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度においてて資本等の額の 20%を超える額の欠損を生じている場合
・最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額(資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額)を上回っている場合
(参考 一般酒類小売業免許審査項目一覧表:https://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/shinki/hambai/s05.pdf)
により、あまりにも資本金額が少額では要件をクリアすることができないのです。5万円の資本金でも会社は設立できますが、酒販免許を申請するなら、資本金額はなるべく多く用意するに越したことはありません。
もう一点、これは少しテクニック的なことになりますが、新規に会社を設立する場合は、決算までの期間をなるべく先に設定することをおすすめします。設立からすぐに決算という流れになると、税務署はその数字を額面どおりに受け取ってしまう可能性があります。免許の申請時と決算が重ならないようにすることで、不要なリスクを避けることが出できます。
しっかり準備すれば酒販免許はとれる
ここまでご紹介してきたように、新規に立ち上げる会社でも、周到に準備をすることで酒販免許を取得することは可能です。酒販免許を取得して、新規に酒販ビジネスを立ち上げようと考えている方は、まずは税務署、または酒販免許に強い、当事務所にご相談ください。

全国直営店から酒買取できるのか
リサイクルショップを経営されている方の中では、全国展開されている方もいらっしゃると思います。
全国の直営店で酒を買取を行い、他の店舗への酒の移動や本社へ集めて販売することができるかどうかについて、よくお問い合わせをいただきますが、
この答えは、 『できます!』
なぜなら、同じ会社が運営している以上、店舗間の商品移動や本社へ集めること自体、販売行為ではないからです。
つまり、酒類販売業免許を取得していない店舗で買取を行い、酒類販売業免許を取得している店舗や本社で販売することは酒税法違反でもありません。
しかし、買取を行う店舗でも、同じ顧客から継続的に酒類を買取を行わない、転売目的の酒類の買取を行わない、盗品であるとわかっていて買取を行わないなど法令遵守を確実に行う必要があります。 (さらに…)

全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許に関する申請等手続きの変更
毎年9月1日(土日の場合にはよく月曜日)に卸売販売地域(都道府県)ごとの免許可能件数が国税庁のホームページと各税務署の掲示板等で公開されます。
1ヶ月間の申請等期間(9月1日〜9月30日まで(土日の場合には翌月曜日))で、審査順位は公開抽選により決定します。
申請時には、一部の書類だけでよく、抽選で当選した場合にすべての書類を整え、提出すればよくなりました。 (さらに…)

全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許の提出書類
申請時
酒類販売業免許申請書または酒類販売業免許条件緩和申出書
現在の免許条件と全酒類卸売業免許取得後の免許条件
申請書次葉1「販売場の敷地の状況」
申請書次葉2「建物等の配置図」
チェック表1
審査時
申請書次葉3「事業の概要」
申請書次葉4「収支の見込み」
申請書次葉5「所要資金の額及び調達方法」
チェック表2
申請者(法人の場合は役員全員)の履歴書(酒類販売業免許条件緩和申出の際は不要)
契約書等の写し(土地、建物、設備等が賃貸借の場合は、賃貸借契約書のコピー、建物がまだ未建築の場合には請負契約書等、農地の場合には農地転用許可に係る証明書等のコピーなど)(酒類販売業免許条件緩和申出の際は不要)
土地及び建物の登記事項証明書(酒類販売業免許条件緩和申出の際は不要)
最終事業年度以前3事業年度の財務諸表(酒類販売業免許条件緩和申出の際は不要)
都道府県及び市区町村が発行する納税証明書(酒類販売業免許条件緩和申出の際は不要)
※状況によって添付が省略できる書類もあります。

酒類蔵置所設置報告書
酒類製造者または酒類販売業者が、現在酒類の販売免許を受けている販売場以外に販売の目的で所持する酒類を貯蔵する場所を蔵置場または蔵置所と言います。
この蔵置所を設置する場合には酒税法の規定に基づき、蔵置所を利用する製造場または販売場の所在地の所轄税務署長に対し、『酒類蔵置所設置報告書』により所在地、名称、設置期間、蔵置する酒類の範囲等を報告しなければなりません。 (さらに…)

通信販売酒類小売業免許の販売の仕方
通信販売というとまず思いつくのはインターネット販売やアプリ販売かと思います。
通信販売酒類小売業免許の場合、酒税法に定められている販売方法としてはいくつかあります。
大前提として、2以上の都道府県(例えば、愛知県と静岡県)以上の消費者を対象として販売することが必要です。
この大前提を踏まえたうえで販売方法としては、 (さらに…)

日本で販売されていないお酒を輸入する場合
日本でまだ販売されていないお酒を輸入する場合、お酒の免許取得以外にさまざまな手続が必要になります。
その手続は輸入酒類卸売業免許取得と税関での事前教示、ラベル表記について事前教示などが必要になります。
さらに国内でネットショップなどの通信販売をされるご予定の方は、通信販売酒類小売業免許の取得も必要となります。
必要な手続の手順は以下のようになります。 (さらに…)

梅酒(リキュール)、日本酒、ウイスキーを輸出するための免許
梅酒(リキュール)やウイスキーを輸出するための免許は、『全酒類卸売業免許』『洋酒卸売業免許』『輸出酒類卸売業免許』のいずれかが必要となります。この全酒類卸売業免許は各都道府県ごとで毎年交付可能件数が決められており、なかなか取得が難しいですが、洋酒卸売業免許や輸出酒類卸売業免許については、免許交付可能件数は定められておらず、免許取得が可能な免許になります。
輸出酒類卸売業免許
この輸出酒類卸売業免許を取得するためには、法人であれば役員、個人であればその個人の今までの事業経験や職務経験などと『輸出することが確実であると認められるもの』がひとつの判断基準となっています。
『輸出することが確実であると認められるもの』については、日本酒、焼酎を輸出するための免許でも書いておりますが、海外の取引予定先と仕入(卸免許取得業者または蔵元)の取引予定先との取引承諾書によって証明します。
その取引承諾書は、ガチガチの契約書のような形式ではなく、『〇〇が販売予定している酒類を売買することについて承諾する。』『〇〇が輸出酒類卸売業免許を1年以内に取得しなければ失効する。』などといった簡単な覚書程度で大丈夫です。
海外の取引予定先との取引承諾書は、基本的には英文で作成する必要がありますが、相手先の言語でもよく、取引予定先が日本語を熟知している場合には日本語で作成されてもよいです。
※英文や相手先の言語で作成された場合は、和訳分の添付も必要となります。
事務所等の販売場について
輸出酒類卸売業免許の申請にあたり、事務所等の販売場が必要となりますが、いざ輸出をされる場合には、倉庫を借りるまたは蔵元から直送されることが多いと思いますので、申請の際に大掛かりな倉庫は必要ありません。
当事務所で申請したケースですと、1〜3人程度のオフィスでも免許交付されたこともありますので、そこまで気にする必要はありません。
ただ、マンション、アパート等の共同住宅ですと管理組合や大家さんの承諾が必要となります。
免許に付される販売条件
免許には、販売する条件が付されます。
輸出酒類卸売業免許の場合で梅酒とウイスキーを輸出するときは、『酒類の販売方法は自己が輸出するリキュール及びウイスキーの卸売に限る。』のような販売条件が付きますので、日本酒、焼酎を販売されたい場合には、それらも仕入先、海外の販売先から取引承諾書をもらっておくとよいでしょう。
日本酒、焼酎、梅酒、ウイスキーを輸出する場合は、『酒類の販売方法は自己が輸出する清酒、単式蒸留しょうちゅう、リキュール及びウイスキーの卸売に限る。』などの販売条件となります。
洋酒卸売業免許
この洋酒卸売業免許は、ワインや梅酒、ウイスキーやブランデーなど日本酒、焼酎、ビール、みりん以外の酒類を卸業者や小売業者へ販売ができる免許になります。
これら洋酒に該当する酒類なら、国内販売も輸出もできる免許です。
免許取得のための経験条件ですが、法人であれば役員、個人であればその個人が『酒類の販売業に直接従事(従業員として)した経験が3年以上または、調味食品等の販売業の経営経験が3年以上』等、輸出酒類卸売業免許とは少し違い、具体的に例示されています。
ただし、あくまで例示の規定になりますから、これに合致する必要はなく、今までの事業経験などから総合的に判断されます。
事務所等の販売場について
これも輸出酒類卸売業免許と同じで、倉庫については免許交付後に借りる予定でも申請は可能です。
免許に付される販売条件
洋酒卸売業免許の場合は、『酒類の販売方法は、果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、スピリッツ、リキュール及び雑酒の卸売に限る。』のような販売条件になります。
全酒類卸売業免許
すべての酒類を国内販売、輸出を問わず卸売ができる免許になります。
毎年9月にその年度の免許交付可能件数が発表され、抽選申込は申請によって行います。
競争率も高い免許になりますし、年間販売数量100kl(500mlだと20万本程度)の販売を見込んでいなければなりません。
現在では新規でいきなり申請される方はほとんどなく、この100kl以上の販売実績がすでにあるような卸業者やこれから多くの販売を見込むことができる卸業者が申請されています。
まとめ
梅酒やウイスキーを輸出するためには、『全酒類卸売業免許』『洋酒卸売業免許』『輸出酒類卸売業免許』のいずれかの取得が必要ありますが、この中でも一番ハードルが低く、使いやすい免許は『輸出酒類卸売業免許』でしょう。

販売場の移転許可
販売場の移転許可の効力について
酒類販売業者が販売場を移転しようとする場合は、あらかじめ移転前の販売場の所在地を管轄する税務署長を経由して、移転先の販売場の所在地を管轄する税務署長に対し、酒類販売場移転許可申請書を提出し、申請しなければなりません。 (さらに…)

平成24年日本酒と焼酎の輸出量
平成24年に海外に輸出された酒類の販売額は前年比8.5%増の206億円となりました(国税庁データ)
日本酒輸出は3年連続で伸びてます。
日本酒輸出金額は8946百万円で輸出量14131キロリットル、焼酎の輸出金額は1731百万円で輸出量2781キロリットルで前年比を上回る輸出量と輸出金額になっています。また輸出先の上位は1位米国、2位韓国、3位香港。
韓国への日本酒輸出量は過去最大となり、ヨーロッパでも日本酒は好調であることから、海外での日本酒、焼酎人気がよくわかります。
最近は日本だけでなく、海外からも中国やタイ、インドネシアなどアジア各国へ日本酒、焼酎を輸出されたいという問い合わせも多くいただきます。
それだけ日本酒や焼酎が注目されているということですね。

全酒類卸売業、ビール卸売業免許可能件数
全酒類卸売業免許とビール卸売業免許可能件数が公開されました。
詳しくはこちらをご確認ください。

米トレーサビリティ法について
正式な名称は米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律といいます。
この法律は、平成22年10月1日から取引情報等の記録の作成・保存が施行されております。
対象となる酒類は、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりんです。
酒類製造業者は米の入荷の記録・保存、対象酒類の出荷記録・保存義務が課され、酒類卸売業者や酒類小売業者、料飲店には、対象酒類の入出荷の記録・保存をしなければなりません。
この「取引情報等の記録の作成・保存」とは、
事業者間取引の際に、事業所ごとに米穀等の数量、年月日、相手方の氏名(名称)等に関する入出荷の記録を作成・保存しなければなりません。
さらに平成23年7月1日からは米穀等の原料米の産地を事業者及び一般消費者に伝達する義務が課せられました。
産地の表記方法は、国内産であれば「国産」、外国産であれば国名「〇〇産」とします。
※産地が国内の場合には都道府県名(〇〇県産)や一般的に知られた地名(魚沼産)などでもよいです。
伝達する方法としては、商品に産地情報が記載されたラベルを貼る方法が基本になります。
その他にも、商品ラベルにホームページアドレスや、QRコード等を記載し、これらにアクセスさせることにより産地情報を入手できるようにする方法や商品に相談窓口(電話番号等)を記載し、電話等により産地情報を確認できるようにする方法または、販売店(小売店)の店頭での説明により産地情報を伝達する方法があります。
※相談窓口や店頭での説明の場合、あらかじめ対応マニュアルの整備を行う必要があります。

20歳未満の者の飲酒防止のための表示基準
20歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準は次のようになります。
①酒類の陳列場所における表示
酒類の陳列場所を壁によりほかの商品と明確に分離するか、酒類をほかの商品と陳列棚等により明確に区分した上で、酒類の陳列場所のの見やすい場所に、『酒類の売場であること』または『酒類の陳列場所であること』及び『20歳以上の年齢であることを確認できない場合は酒類を販売しないこと』を表示しなければならない。
(さらに…)

輸出のための酒類蔵置場(倉庫)
原則として、蔵置場設置許可申請書を受理した日(不備または追加書類がある場合には、不備等を補正して再度受理した日)の翌日から起算して、2ヶ月以内に許可が下ります。
申請者は、輸出する酒類を販売することができる酒類販売業者または製造業者であること。
※輸出酒類卸売業免許取得者または酒類製造業免許取得者
蔵置する酒類は、輸出する酒類で、かつ申請場所において詰め替えを行わないものであること。
申請者は、申請前2年内において国税または地方税の滞納処分を受けていないこと
国税又は地方税に関する法令に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、その刑の執行を終わり若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
二十歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律、風俗営業法(20歳未満の者に対する酒類の提供に関する部分のみ)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、暴行、脅迫 等)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり若しくは執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
破産者で復権を得ていない場合またはその他経営の基礎が薄弱であると認められないこと。
申請者が法人であれば役員及び支配人のうち酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと、酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人の取消原因があった日以前1年以内にその法人の役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること、または国税又は地方税に関する法令に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、その刑の執行を終わり若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
二十歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律、風俗営業法(20歳未満の者に対する酒類の提供に関する部分のみ)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、暴行、脅迫 等)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり若しくは執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること。 (さらに…)

輸出酒類の蔵置場について
輸出酒類蔵置場のメリット
輸出酒類の蔵置場(お酒の倉庫)で酒税の免税措置を受けることができます。
輸出酒類卸売業者の場合、仕入の際に蔵元から保税倉庫に直接送ってもらえればこの蔵置場は特に必要はありませんが、自社倉庫などに集め混載して輸出する場合には、蔵置場を設置しなければ酒税の免税を受けられません。
特に輸出商社の場合、蔵置場設置をすると多くのメリットを見込むことができます。
ただし、この蔵置場については、酒類蔵置場許可申請が必要となり、輸出酒類卸売業免許取得業者の場合は、蔵元(酒類製造業者)から経由できる蔵置場は1箇所のみとなります。
そのため、蔵置場から蔵置場へ酒類を移送することもできません。
蔵置場の選定も考慮して行う必要があります。
その他蔵置場設置には、
・容器詰替等のため
・果実酒出荷のため
・製造場移転のため
・原料用アルコールを他の製造者へ移出するため
・製造場以外にお酒を保管するため
・首都圏等の消費が多い地域の共同蔵置場 などでも許可取得することができます。
蔵置場設置許可を受けた場合、許可条件に『蔵置する酒類は、輸出する清酒、単式蒸留しょうちゅう、リキュールで、かつ、その蔵置場で詰替えを行わないものに限る。』という条件が付されます。
酒類蔵置場設置許可の要件
申請者(法人であればその役員)が、税金の滞納処分を受けたことがあるなど様々な要件がありますが、基本的に酒類製造免許や酒類販売業免許を申請される際も、同様の要件が課せられていますので、免許取得後なにもなければ特に人的な要件は大丈夫です。
場所的要件
・蔵置場が酒場、料理店等と同一場所でないこと
※区画わけがきっちりされており、その倉庫が飲食店等から独立した場所などであれば隣接していたとしても大丈夫です。
・酒類製造免許、酒類販売業免許を受けている場所でないこと
※免許交付を受けている場所でしたら、もともとお酒をおくことができるためです。
・他の製造業者の蔵置場(蔵置所設置報告書の蔵置所も該当します。)ではないこと
・常時職員の配置がされている。(業務委託倉庫など業務委託契約でもいいです。)
・蔵置場でお酒の詰替を行わないこと
酒類蔵置所と酒類蔵置場を併設する場合
酒税の免税を受ける酒類と酒税が課税されたまま輸出する酒類がある場合、酒類蔵置所と酒類蔵置場を同じ場所で併設することも可能です。
その場合には、
・酒類蔵置所と酒類蔵置場が明確に区切られていること
・酒税が課税された酒類と酒税が課税されていない酒類が混ざることのないような措置をしていること
これらを満たすことによって、酒類蔵置所と酒類蔵置場は併設することができます。
※倉庫業者に業務委託する場合には、業務委託契約書の内容次第になります。
酒類蔵置場設置許可申請
蔵置場設置許可申請書類は残念ながら、まだ税務署から手引き等が発行されておらず、またもくろみ書などの添付書類についてもひな形も公開されていないので、代行できる行政書士がほとんどいません。当事務所では実績も多数ありますので、安心してご相談いただけます。酒類蔵置場設置許可申請をご検討の方はぜひ一度ご相談ください。
ご相談はこちらから

輸出酒類卸売業免許の改正点
この輸出酒類卸売業免許に関しては、もともと年間販売見込数量自体ありませんでしたので、特に大きな改正等はありません。
契約等により酒類を輸出することが確実であると認められること
輸出酒類卸売業を経営するのに十分と認められる所要資金等を有していること
これらと基本的な要件を満たせば、輸出酒類卸売業免許は申請できることになります。
重要なポイントは【契約等により酒類を輸出することが確実であると認められること】になります。
これは申請時点である程度、どのように酒類を販売するのか、どこに酒類を販売するのか、どこから仕入れを行うのかなど確定していなければなりません。
申請してから免許交付まで2ヶ月程度かかることも考えると、覚書程度でよいので仕入先や販売先と輸出することに関しては確定してもらい、瓶のサイズや内容量、ラベル等に関しては、輸出酒類卸売業免許申請中に打ち合わせを進めて行くことをお勧めします。
【輸出酒類卸売業を経営するのに十分と認められる所要資金等を有していること】に関しては、年間酒類輸出額の2ヶ月分を有していることが必要になります。ただし、資金があればよいわけではなく、経営状況からも判断されます。

輸出入酒類卸売業免許
輸出入酒類卸売業免許には、輸入酒類卸売業免許と輸出酒類卸売業免許があり、
輸入酒類卸売業免許とは、日本にある会社等でお酒を輸入して、酒屋などの酒類小売店へ販売する免許です。
またお酒を直接輸入し、直接飲食店への販売の場合は、『一般酒類小売業免許』が必要となり、お酒を直接輸入し、ネットショップやオークションで販売する場合には、『通信販売酒類小売業免許』が必要となります。
輸出酒類卸売業免許とは、日本からお酒を輸出する場合に必要な免許です。
酒税法は国内法であることも考えると、必要な免許について、直接海外の飲食店や消費者へ販売する場合は『一般酒類小売業免許』、通信販売で海外の消費者へ販売する場合には、『通信販売酒類小売業免許』ですが、仕入れの問題や税務署の酒類指導官の解釈の違いもあるので、注意してください。
輸入酒類卸売業免許
この免許は、ワイン、ウイスキーなどのお酒を輸入するために必要な免許ではなく、自社で輸入したお酒を酒屋さんなどの小売店へ販売をするための免許です。
ですから、輸入したお酒を通信販売で一般消費者に販売するだけの場合には、通信販売酒類小売業免許だけ取得すれば大丈夫です。
同じように、輸入したお酒を飲食店だけ、店頭販売だけへ販売する場合には一般酒類小売業免許だけ取得すれば足ります。
この輸入酒類卸売業免許を取得するためには、個人であればその方自身、法人であれば役員の方の今までの経験に加え、お酒以外の商品等で輸入や輸出など海外との取引があるか、実際にお酒を輸入し、販売することが確実であると認められるかが、免許取得のポイントになってきます。
実際に私が申請をさせていただいた案件では、申請者の経験よりも海外との取引が確実かどうかが一番のポイントになっています。
この海外との取引が確実であるかというのは、申請者個人または役員の方の今までの職歴や事業経験、免許申請時に取引予定先がほぼ確定しているかを示すため、輸入元との取引承諾書と国内販売先の取引承諾書が必要となります。
その他繰越の欠損が多いと免許取得が難しいなどの決算内容の条件、事務所を構える場所の条件等があります。
当然輸入されるので、在庫を保管しておく倉庫が免許申請のために必要と思われる方もいるかもしれませんが、倉庫については免許取得後に、蔵置所設置報告書を提出することになりますので、免許申請時には事務所だけで大丈夫です。
輸出酒類卸売業免許
この免許は、日本酒や焼酎、ウイスキーなどを輸出し、海外の小売店や卸業者(バイヤー等)に販売することができる免許です。
免許自体に、『酒類の販売は、自己が輸出をする清酒、単式蒸留しょうちゅうの卸売に限る。』というような条件がつきますから、輸出でしかお酒を販売することができません。
またこのような条件のない全酒類卸売業免許や洋酒卸売業免許などでは、国内でも海外でも卸売することができますので、これらの免許を取得済みの方は、新たにお酒輸出のために輸出酒類卸売業免許を取得する必要はありません。
この輸出酒類卸売業免許取得のためには、輸入酒類卸売業免許と同じように申請者の方、法人であれば役員の方の今までの職歴や事業経験で輸出経験があるか、輸出することが確実であると認められるかがポイントとなってきます。
輸出することが確実であるかどうかは、輸入酒類卸売業免許と同じように、輸出販売予定先の取引承諾書、仕入予定先の取引承諾書が必要となってきます。
その他直前の決算期の繰越欠損が資本金等の額を超えていないこと、過去3期連続して資本金等の額の20%を超える赤字を出していないことなどの条件があります。
倉庫に関しては申請時は不要で、免許取得後必要があれば蔵置場設置許可申請書を提出することになります。蔵置場設置することにより、酒税が免税となることもありますので、蔵置場設置許可申請をされていない方は、一度ご検討ください。また蔵元から仕入を行う場合は、蔵元から直接輸出を行うことになりますので、倉庫は必要ないです。
輸出酒類卸売業免許、輸入酒類卸売業免許、蔵置場設置許可申請を当事務所では全国でも実績が多数ありますので、ご検討の方はぜひ一度お問い合わせください。

輸出入酒類卸売業免許の改正点
平成24年9月1日より経営基礎要件の年間販売見込数量について緩和され、今まで年間販売数量6㎘であったのが廃止され、申請がしやすくなります。
この輸出入酒類卸売業免許については、初めて酒類販売業免許を取得される方が、一番取得しやすい免許でしたが、年間販売数量が廃止となったことでさらに取得しやすくなりました。
契約等により酒類を輸入や輸出することが確実であると認められること
これは輸入元や輸出先との取引承諾書、国内仕入先や国内販売先との取引承諾書により証明します。
輸出入酒類卸売業を経営するのに十分と認められる所要資金を有していること
概ね2か月分の運転資金と仕入資金を証明します。
これらの他に人的要件等を満たすことで免許の申請が可能になります。

輸出免税
日本国内で製造されている日本酒や焼酎などを海外へ輸出されたい場合、輸出酒類卸売業免許という免許が必要になります。
また、海外の飲食店に直接販売したい場合には、その販売したい国で酒類販売免許(リカーライセンス)等が必要になることもあります。
※アメリカなど、州ごとに必要になる場合があります。
ただし、酒類の製造業者以外が輸出用の酒類在庫を保管する場合には、蔵置場を設置しなければ輸出免税の適用がありませんので注意が必要です。
※輸出業者が在庫保管をせず、あらかじめインボイス番号を取得した酒類を仕入れ、輸出する場合には蔵置場設置する必要はありません。
なお、輸出についてですが、輸出する目的で、酒類をその製造場または蔵置場から輸出する場合、日本の法適用地域以外に酒類を移出することとなります。日本の法的用地域以外とは、例えば外国籍の船舶や航空機に船用品または機用品として酒類を積み込む場合を言います。
ただし、外国籍の船舶や航空機であっても日本人が船主と船舶の賃貸借契約に基づいて船体のみを賃借(いわゆる裸用船し、日本人の船長または乗組員を使用している場合など、実質的に日本国籍を有する船舶又は航空機と同様に使用されていると認められるものは含みません。
輸出免税を受けるための条件 (さらに…)

洋酒卸売業免許で販売できる酒類について
洋酒と聞くと海外のウィスキーやブランデー、ワインなどのお酒だけを想像しがちですが、実は酒税法上、国産のお酒も卸売することができます。
それでは洋酒というのはどんなお酒のことなのでしょう。
洋酒卸売業免許で販売できる酒類
洋酒卸売業免許で販売することができるお酒は、次の10酒類あります。
酒税法上の酒類
代表的なお酒
果実酒
カベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン、メルロー、マスカットベリーA(赤ワイン)
リースリング、シャルドネ、セミヨン、ソーヴィニヨン・ブラン、甲州(白ワイン)
その他ロゼワイン、スパークリングワイン(シャンパン)など
甘味果実酒
フォーティーファイドワイン、アロマタイズドワイン(フレーバーワイン、混合ワイン)、
シェリー、ポート、マディラ、ベルモット、スイートワインなど
ウィスキー
スコッチウィスキー、アイリッシュウィスキー、アメリカンウィスキー、日本のウィスキー
山﨑、白州、余市、ジャックダニエル、クラウン・ローヤル、響、ロイヤル・サルートなど
ブランデー
コニャック
XO、カミュ、ヘネシー、レミー・マルタンなど
発泡酒
輸入ビール、第3のビール等
その他の醸造酒
蜂蜜酒、黄酒
スピリッツ
ジン、ウォッカ
リキュール
梅酒、マッコリなど
粉末酒
現在はあまりありません。
雑酒
紹興酒など
このように洋酒とはいても国産のお酒もあります。
また上記の例にあげたお酒であっても、違う酒類の品目になる場合もあります。
これは酒税法上、酒類の製造方法、その成分により分類しているためです。
例えば、マッコリは清酒に該当することもありますので、注意してださい。

洋酒卸売業免許の改正点
平成24年9月1日より洋酒卸売業免許の要件が緩和されます。
大きな改正としては、年間販売見込数量が24㎘(大都市では36㎘)であったのが、年間販売見込数量自体が廃止となります。
これにより、財産的な要件も緩和され、申請がしやすくなります。
ただ、洋酒卸売業免許については加重される要件もあります。
それが経験要件です。 (さらに…)
お電話でのお問い合わせ 0120-961-278(毎日09:00~21:00)
0120-961-278(毎日09:00~21:00)
 0120-961-278(毎日09:00~21:00)
0120-961-278(毎日09:00~21:00)
過去酒販免許申請した地域
愛知県全域、名古屋市、豊田市、岡崎市、豊橋市、静岡県全域、浜松市、焼津市、静岡市 、三重県全域、四日市市、津市、鈴鹿市、伊勢、岐阜県全域、岐阜市、大垣市、関市、東京都全域、大阪府全域 北海道旭川市、札幌市、青森県、高知県、秋田県、福島県、宮 城県、仙台市、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、新潟県、富山県、長野 県、和歌山県、奈良県、京都府、滋賀県、石川県、富山県、高知県、愛媛県、兵庫県、姫路市、神戸市、福岡県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県全域
お急ぎの申請にも対応しております、どうぞお気軽にご相談ください。
愛知県全域、名古屋市、豊田市、岡崎市、豊橋市、静岡県全域、浜松市、焼津市、静岡市 、三重県全域、四日市市、津市、鈴鹿市、伊勢、岐阜県全域、岐阜市、大垣市、関市、東京都全域、大阪府全域 北海道旭川市、札幌市、青森県、高知県、秋田県、福島県、宮 城県、仙台市、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、新潟県、富山県、長野 県、和歌山県、奈良県、京都府、滋賀県、石川県、富山県、高知県、愛媛県、兵庫県、姫路市、神戸市、福岡県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県全域
お急ぎの申請にも対応しております、どうぞお気軽にご相談ください。